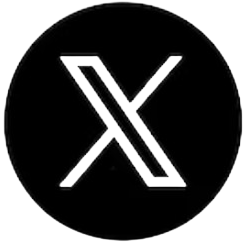私の名刺には、「歩行訓練士」という肩書が記載されています。
名刺交換をすると、「理学療法士のような仕事ですか?」「高齢者が歩けるようになる訓練をするのですか?」とよく聞かれます。
皆さんは、歩行訓練士をご存知でしょうか?
歩行訓練士とは、視覚障害者の生活に関する訓練を行う民間資格です。
まだ認知度が低い「歩行訓練士」
歩行訓練士の資格が取れるのは、日本で2か所だけです。ひとつは埼玉県の“国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科”。もうひとつは、大阪の“社会福祉法人日本ライトハウス”です。
私は、埼玉県の国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科で資格を取り、神奈川県ライトセンターで、2年間歩行訓練士の業務に従事しました。
歩行訓練士の有資格者は800名弱と、まだまだ認知度が低いのが課題です。

私は現在、歩行訓練士としての業務は行っておらず、株式会社mitsukiの代表をしています。
同行援護事業所の運営、Webメディア「Spotlite」の運営、同行援護事業所向けの業務支援システム「おでかけくん」の開発と販売など、視覚障害に関わる事業を行っています。普段、経営に関する打ち合わせや対外的な業務が多く、歩行訓練士として現場に出ることはありません。
そんな私が、今年7月に仙台で行われた日本歩行訓練士会の夏季研修会に参加したことをきっかけに、自分の役割を考え直し、色々な視覚障害者団体の活動に関わるようになりました。
今回は、現場から離れた私が歩行訓練士として改めて感じたことやこれから取り組みたいことをお伝えします。
研修会をきっかけに「歩行訓練士」の役割をとらえなおす
「大切なのは、歩行訓練士自身が、歩行訓練士の役割を理解すること」
仙台での研修会後、大先輩の言葉が、しばらく頭から離れませんでした。
歩行訓練士の役割とは、何なのか?
歩行訓練士の仕事は、白杖などを用いた歩行訓練、調理や掃除などの日常生活訓練、パソコン訓練などを通して、視覚障害者の自立を支援することです。

しかし、これらは日常の業務であって、本来の役割と言えるのでしょうか。もっと広い視野で考えなければいけないような気がしていました。
数日後、ふと「もっと色々な役割があるかもしれない」と気づきました。
例えば、歩行訓練のことを知らない視覚障害者や眼科医、行政機関などに、歩行訓練士の存在を知ってもらうこと。福祉に関心のある学生や社会人に、職業の選択肢として、歩行訓練士の業務に関心を持ってもらうこと………。直接視覚障害者の支援に関わらなくてもできることはたくさんあります。
これらを自分の役割だとは思わず、「今は会社の仕事が忙しいから、歩行訓練はできない」とどこか他人事で、歩行訓練士という肩書から目を背けていました。
私自身、歩行訓練の現場業務から離れて7年が経ちました。
視覚障害者に訓練を行うだけが歩行訓練士の仕事ではなかったことに気づくと、これまで何もできていなかった自分が急に恥ずかしくなりました。
「歩行訓練士」についてもっと発信したい
私たちが運営するWebメディア「Spotlite」は、月間3万人が閲覧しています。視覚障害に特化したWebメディアでは最大規模です。
もし、「Spotlite」で歩行訓練士のことを発信することで、視覚障害者が1人でも自立訓練を受けてくれたら?福祉に関心のある学生が、1人でも歩行訓練士を目指してくれたら?
もっと私にできることがあるかもしれません。
そんなことを考えているとき、歩行訓練士の先輩がお声をかけてくださいました。毎年1回開催される視覚障害リハビリテーション研究大会の実行委員会のメンバーに加わることになったのです。
現在は、来年のプログラム内容を検討している段階ですが、私がこれまで会社で取り組んできたことに関連するテーマも取り上げられそうです。
仙台での研修会をきっかけに、私の役割とやるべきことが少しずつ見えてきたような気がします。

技術の継承も視野に、より広い視点でできることを。
一方、少し懸念点もあります。それは、歩行訓練士の技術の継承です。
福祉業界は支援者も含めて高齢化が進んでおり、同年代の仲間と出会う機会は限られています。歩行訓練士は、暑い日も寒い日も、視覚障害者と一緒に外を歩きながら指導することが多く、非常に体力の必要な仕事です。
数年、数十年と月日が流れ、経験とスキルを兼ね備えた歩行訓練士が引退したあと、現役の歩行訓練士に技術を継承していかなければいけません。
私も気づけば、30代の中盤に差し掛かりました。私が歩行訓練の現場に戻る可能性は極めて低いと思います。ただ、会社の代表としての役割を果たすことは大前提の上で、2025年はさらに視覚障害業界全体を見据えた取り組みをしていきたいと考えています。
例えば、私と同年代や後輩の歩行訓練士とのネットワークを作り、相互に技術を学ぶ機会を設けておくといいのではないか……。そんなことを考えています。
また、歩行訓練士や視覚障害リハビリテーションに関するイベントを企画したり、「Spotlite」で歩行訓練士をテーマに連載を始めてみたりする施策もできそうです。
より本格的に関わるためには、日本歩行訓練士会や視覚障害リハビリテーション協会の役員、もしくは理事という立場を目指すことも必要なのかもしれません。
現在はまだまだ素質も余裕もありませんが、長期的に、視覚障害者の業界が少しでもよりよくなるような選択をしていきたいです。
数年後、「この記事を読んで、歩行訓練士になりたいと思いました」という未来の歩行訓練士が生まれることを信じて、私なりに社会との接点を考えていきます。

記事内写真撮影:Spotlite(※注釈のあるものを除く)
編集協力:株式会社ペリュトン