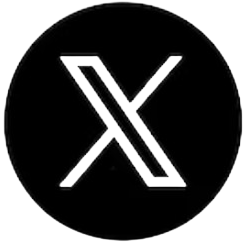2022年11月、視覚障害者向けサービスを展開する6社で構成する「Blind Entertainment Technology(略称:BET)」のメンバー4名がシンガポールへ訪問しました。
シンガポールへの訪問が実現したのは、現地でダイバーシティ&インクルージョンの推進に取り組むNPO法人「TomoWork」の皆様のアテンドがあったからこそです。
CEOの百田牧人さんを中心に、各施設とのアポイントや取材対応など、多大なるご尽力をいただきました。
TomoWork(外部リンク)
今回は、障害者の総合施設「Enabling Village(略称:EV)」や、視覚障害者団体「Singapore Association of the Visually Handicapped(略称:SAVH)」、身体障害者団体「Handicaps Welfare Association(略称:HWA)」などを訪問し、現地の視覚障害者を取り巻く環境を肌で感じました。
その中でも視覚障害者団体「SAVH」で、施設の代表者と3名の視覚障害者にインタビューした内容を中心に、シンガポールでの視覚障害者福祉の現状をお伝えします。

SAVHとは
1951年に設立された視覚障害者の全国的な福祉団体です。視覚障害者が新しいスキルを習得し、自立して社会に適応できるよう支援することを使命とし、福祉機器の斡旋や職業訓練、マッサージサービスからロービジョンケアまで、幅広く活動しています。
シンガポールは、人口約545万人のうち、約5万人の視覚障害者がいるそうです。
今回の訪問では、SAVH代表のベンジエさんと、視覚障害者のジェイソンさん(男性)、リンさん(女性)、ジョシュさん(男性)3名に、日本の各社の製品やサービスを紹介したあと、インタビューを行いました。

日本の製品・サービスへの反応
歩導くんガイドウェイ、Ashirase(アシラセ)、HELLO! MOVIE(ハロームービー)、同行援護研修の4つの製品・サービスをご紹介し、フィードバックをいただきました。
歩導(ほどう)くんガイドウェイ
概要
「歩導くんガイドウェイ」は、白杖で叩いたときの床面との音や質感の違い、足裏から伝わる感触の違いによって、視覚障害者を目的地まで安全に誘導する歩行誘導マットです。
(引用:歩導くんガイドウェイ webサイト)

フィードバック
「点字ブロックのように、視覚障害者には優しいが車椅子ユーザーやベビーカーを押す親御さんなどにはバリアになる製品よりも、インクルーシブなものが社会で広まってほしい」という思いが根底にあるようです。「ぜひ、白杖での使用感や踏み心地など、実際の使い勝手を経験してみたい」という声がありました。
特に、進路が交差する場所での分岐のわかりやすさに質問が集中しました。最後には、「導入にあたっては、屋外であれば交通局、屋内であれば建築局の管轄になるので、規制などをよく調べた方がよい」という設置に向けての現実的なアドバイスをいただきました。
Ashirase(あしらせ)
概要
視覚障がい者の単独歩行を支援するナビゲーションシステムです。スマートフォンアプリによる音声入力や案内および、お使いの靴につける振動インターフェースで構成されています。
(引用:Ashirase webサイト)
フィードバック
「靴に装着したデバイスがどのようにナビゲートをしてくれるのか、ぜひ実機を試したい」という反応が多々ありました。また、目的地のビルに到着した後、目的の店に到着するまでの流れについても質問がありました。Ashiraseの徳田さんによると、現状は「GPSで案内する仕組みのため、屋内に移行した後は別のソリューションが必要になる」とのこと。例えば、歩導くんガイドウェイと組み合わるなど、現時点でできる工夫次第で可能性が大きく広がりそうです。
HELLO! MOVIE(ハロームービー)
概要
HELLO! MOVIEアプリは、スマホやスマートグラスで映画の字幕と音声ガイドを楽しめる無料アプリです。視覚障害者は、観たい映画のガイドデータを事前にダウンロードしておくと、イヤホンから映画の解説を聞くことができます。アプリの詳細やダウンロードについては、下記公式サイトをご確認ください。
(参照:HELLO! MOVIE アプリ公式サイト)
フィードバック
SAVHではCDによる音訳映画の貸出を行っているそうですが、それほど利用率が高い様子ではありませんでした。「もし、みんなでインクルーシブな映画を見に行くことができれば、会話が増え、お互いの関係性の構築にも繋がるので画期的である」と、非常に前向きな反応がありました。こちらも「ぜひ体験をしてみたい」という声がたくさんあり、映画館での上映体験会など次のアクションにつながりそうだと感じました。
同行援護研修
概要
同行援護のガイドヘルパーのための資格研修です。移動が困難な視覚障害者の外出をサポートするため、障害の理解をはじめ、視覚的情報提供や代筆・代読の技術、移動の援護、排泄・食事等の支援に関する知識・技術を習得します。
(参照:東京都保健福祉局ふくむすびwebサイト)

フィードバック
SAVHでは3週間のガイドヘルパー養成講座を行っているとのことでした。日本では現状、講義12時間と演習8時間の合計20時間、3日間程度の受講で資格が取得できるという話を聞き、「ぜひ講習内容が知りたい」という反応がありました。シンガポールと日本での公的制度の共通点と相違点を詳しく調べることで、より具体的なアクションにつながりそうです。
日本の製品・サービスへの反応 まとめ
日本の各製品・サービスについて、総じて前向きな反応をいただきました。
「実際に体験したい」という声が多くあったので、次回訪問する機会を設けられた際には、ぜひ体験会などを企画したいと感じました。
一方、実際に導入するにあたっては、法律や文化の違いなど多角的な視点での検証が必要です。今後のサービス向上につながる大きな気づきをいただくことができました。
SAVH代表・ベンジエさんインタビュー
SAVH代表のベンジエさんに、視覚障害者が最初に施設へつながる流れと福祉機器の購入手順についてお話いただきました。

ー視覚障害者はどのような流れで、SAVHのことを知るのですか?
シンガポールではすべての視覚障害者が、SAVHにつながります。総合病院やクリニックの眼科医から推薦書をもらい、紹介を受けます。SAVHに紹介された視覚障害者は、会員登録を行うと、様々なサービスが利用できます。
―SAVHではどのようなサポートが受けられるのですか?
まず、SAVH内のロービジョンクリニックで、眼科医が本人の疾患や見え方を診察したあと、ニーズをアセスメントします。本人に必要な支援が把握できれば、補助機器センターで福祉機器を選定するという流れです。
ー補助機器はどのように購入するのですか?
視覚障害者が福祉機器を購入する際には、「アシスティブテクノロジーファンド」という政府の助成金から、価格の90%が補助されます。これは、全ての視覚障害者が利用できます。
金額は1人あたり、一生涯で4万シンガポールドル(日本円で約400万円)という上限があります。
ー助成金の対象となるかどうかは、どのように判断されるのですか?
福祉機器とシンガポールにおける障害者の中心的な機関であるSG Enableが最終的に承認すれば、補助金がおります。SAVHは、SG Enableに対して、本人の必要性などを伝えるなど、連携して対応しています。
視覚障害者インタビュー
シンガポールでの視覚障害者の仕事や移動手段、余暇活動などの現状について、ジョシュさん(男性)、リンさん(女性)、ジェイソンさん(男性)の3名にお話いただきました。

ーシンガポールでの視覚障害者のお仕事の現状について教えて下さい。

今は点字製作センターの職員として、学校の教科書やSAVHの利用者から依頼があった本を点訳する仕事をしています。私は、20歳の時に緑内障で失明し、同時に仕事も失いました。そんな時、SAVHに出会い、白杖を使った歩行訓練を行ったことで自分が自立して生きていけることを実感できました。さらに点訳の仕事にも就くことができました。同じ立場の視覚障害者や、学校の生徒の役に立てることが嬉しく、今は自分の仕事に達成感を覚えています。
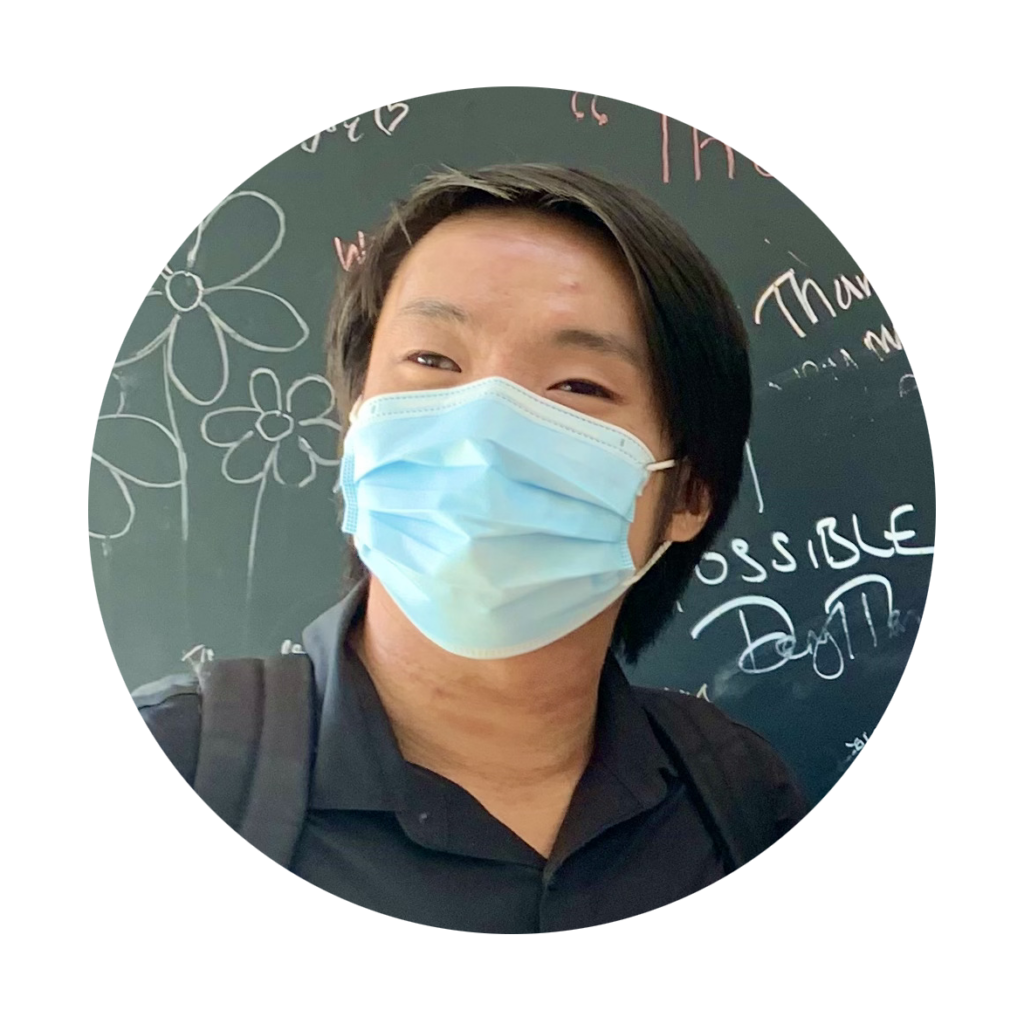
今私は、デジタルアクセシビリティに関する仕事をしています。業務内容は、視覚障害者のためのソフトウェアを作ることです。業務上、必要な時は外出しますが、基本的に在宅で働いています。
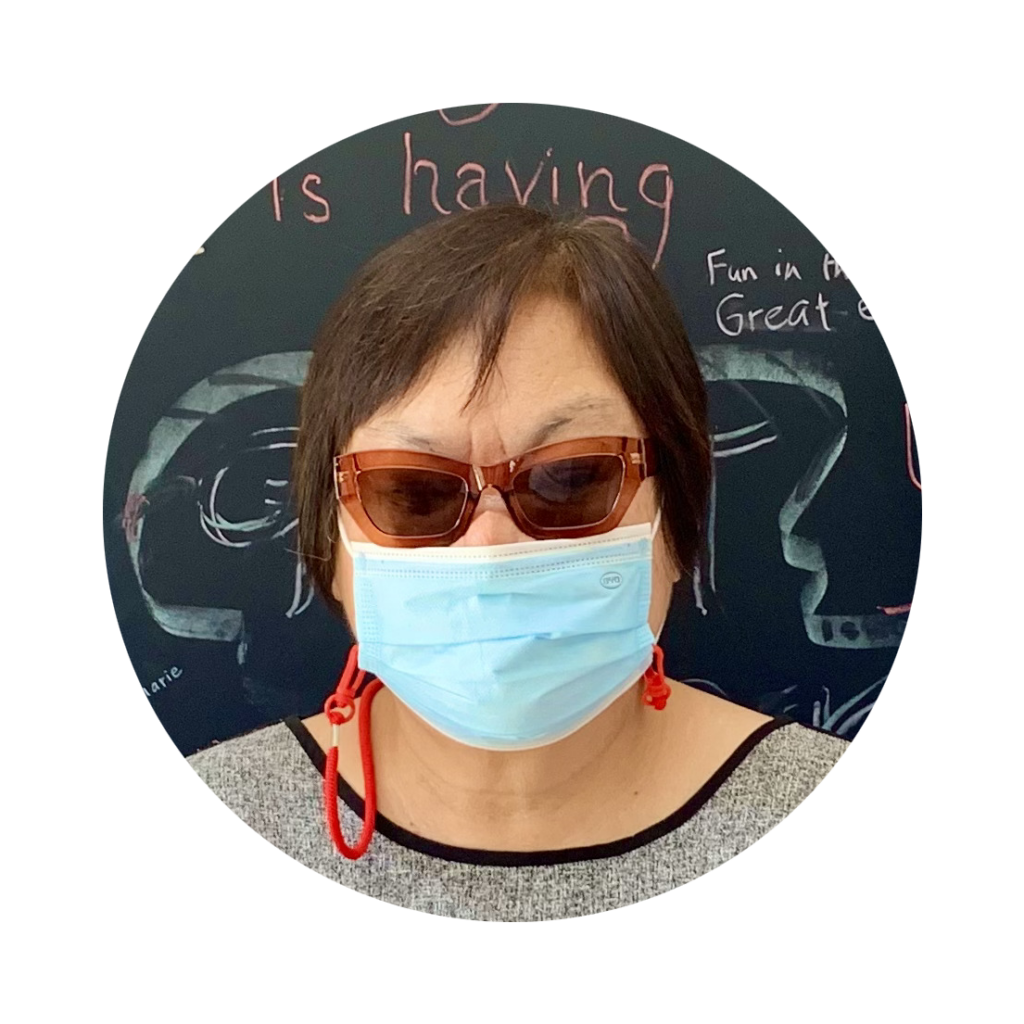
お仕事の話の前に、私の見え方について少しご説明します。私は中途視覚障害者で、11歳から少しずつ視力が低下し、現在は全盲です。ロービジョンのときには、比較的仕事が見つけやすかったです。私は、電話のオペレーターとして働いていました。当時、視覚障害者が働く方法は、電話のオペレーターかSAVHでバスケットを作るという2つの選択肢しかありませんでした。
ー現在は少しずつ職業の選択肢が増えてきているのでしょうか?
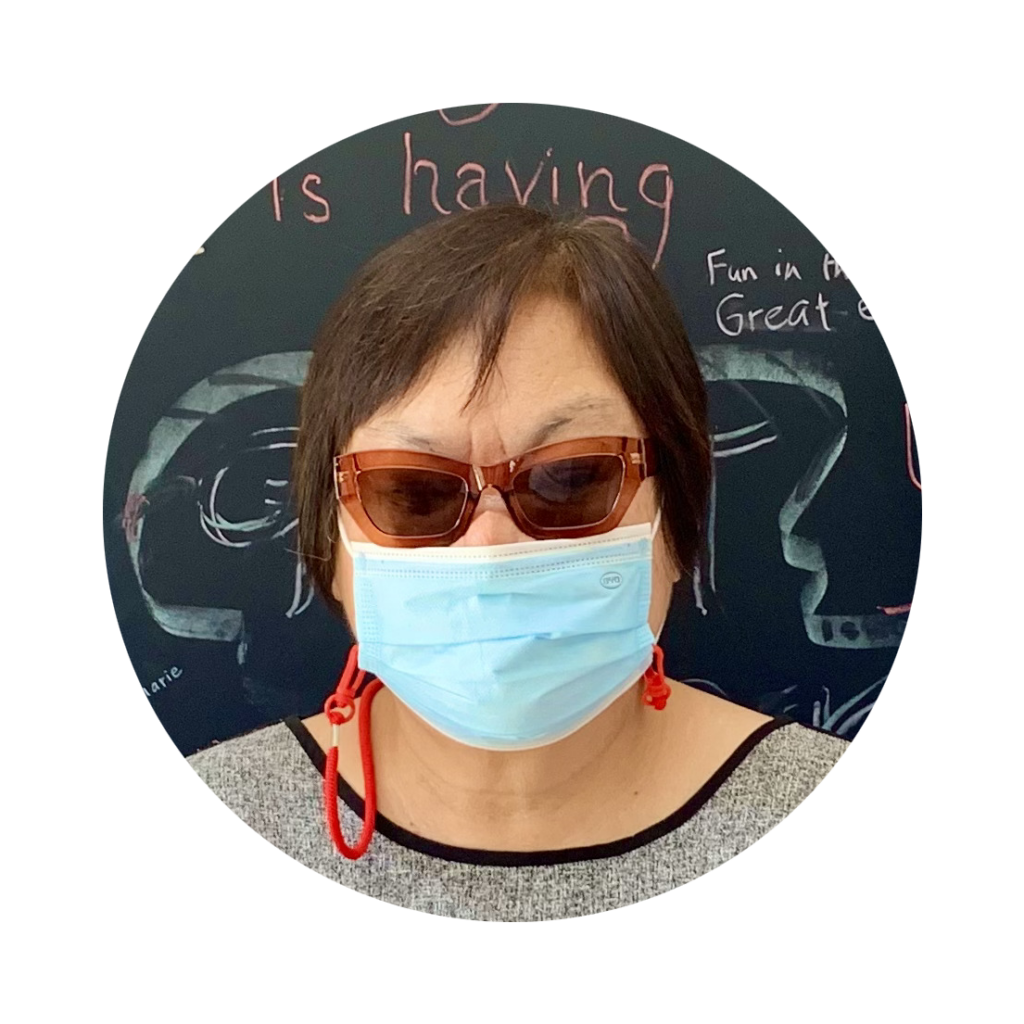
現在は、視覚障害者も大学や専門学校などで教育を受けることができるようになってきています。しかし、企業に就職するのは非常に難しいのが現状です。シンガポールはもっと共生社会を進めなければいけないと思います。私は、もっと政府が障害者の雇用を生むための施策を行う必要があるのではないかと考えています。
ーそうなのですね。就労の課題解決に向けた取り組みは何かあるのですか?
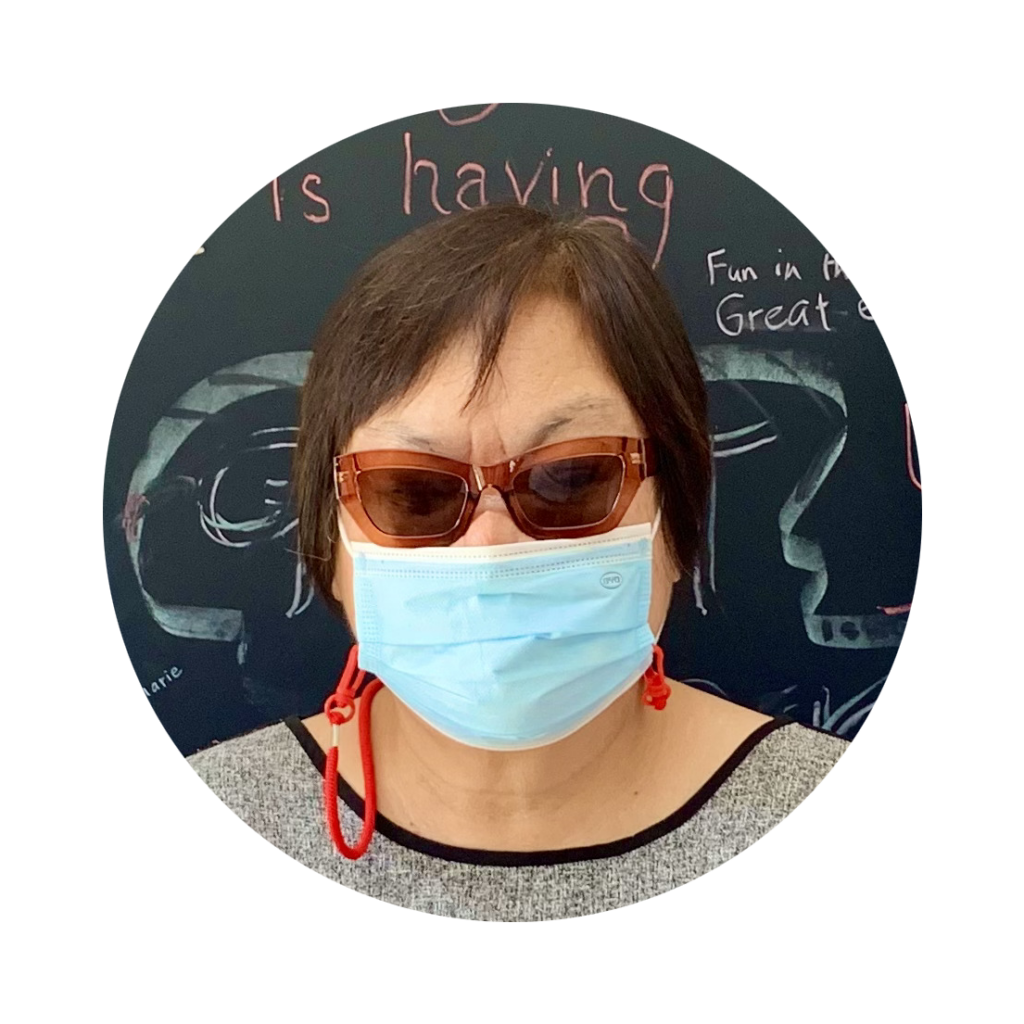
今年の10月15日日曜日には国際白杖デーのイベントがシンガポールでも開催されました。このイベントは、視覚障害者のための「ジョブフェア」という意味合いもありました。初めて民間企業が参加し、障害者雇用の実例などを提案してくれました。ただ、全盲の視覚障害者に対するアクセシビリティはまだまだ発展途上です。

ー日常生活では、どのような困難がありますか?

視覚障害者として困ることは日常的にたくさんあります。例えば、移動です。ショッピングセンターの中で特定のお店に行きたくても場所を見つけることができません。公共交通機関の利用では、バスを利用する際にはバスの番号がわかりません。
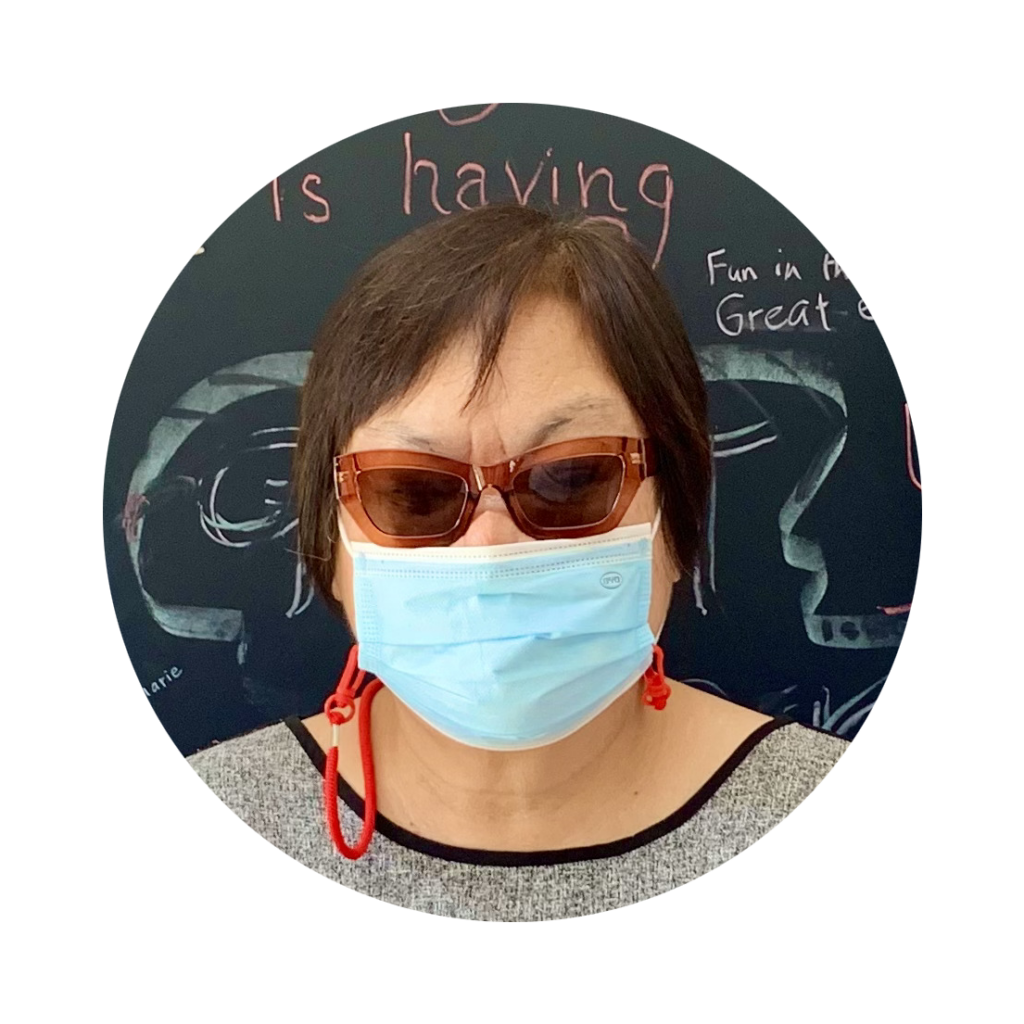
たしかに、移動には大きな困難があります。ただ、前向きな動きが出始めています。例えば、視覚障害者が国土交通庁に働きかけて、電車の駅をもっとアクセシブルに変えようという試みをしています。また、バス利用に関するアプリを作って、バスの番号が分かるようにするプロジェクトも始まっています。

ーたしかに、シンガポールでは公共交通機関での音声案内などが日本に比べて少ないかなと感じました。
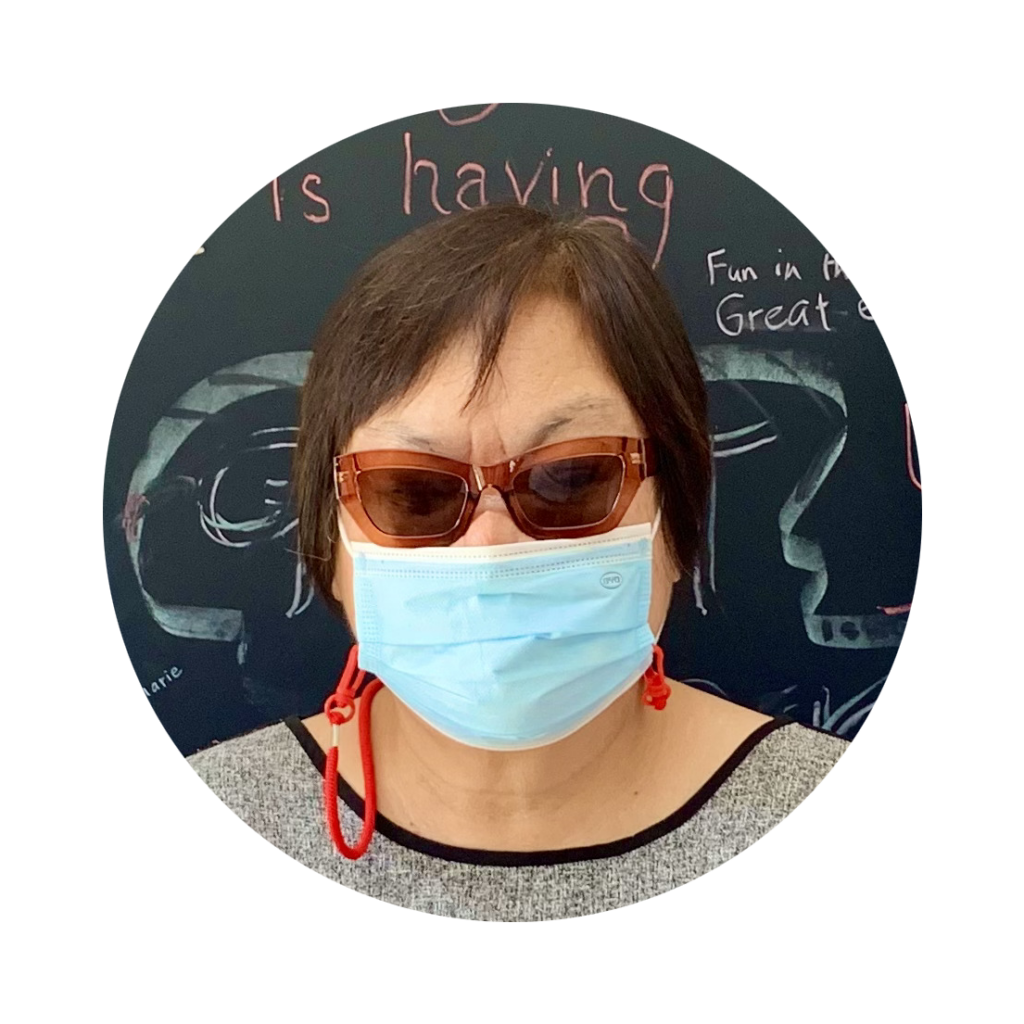
私は東京に行ったことがあり、東京は進んでいると感じました。電車の切符を音声で購入できるのはとても便利でした。ホテルから空港に移動する際は、バスを利用しました。バス停が分からず、英語ができる乗客に行き先を聞かなければならないなど、大変なことはあったのですが、1人で移動することができました。
ーリンさんは、白杖を使って1人で色々なところに行かれているのですか?
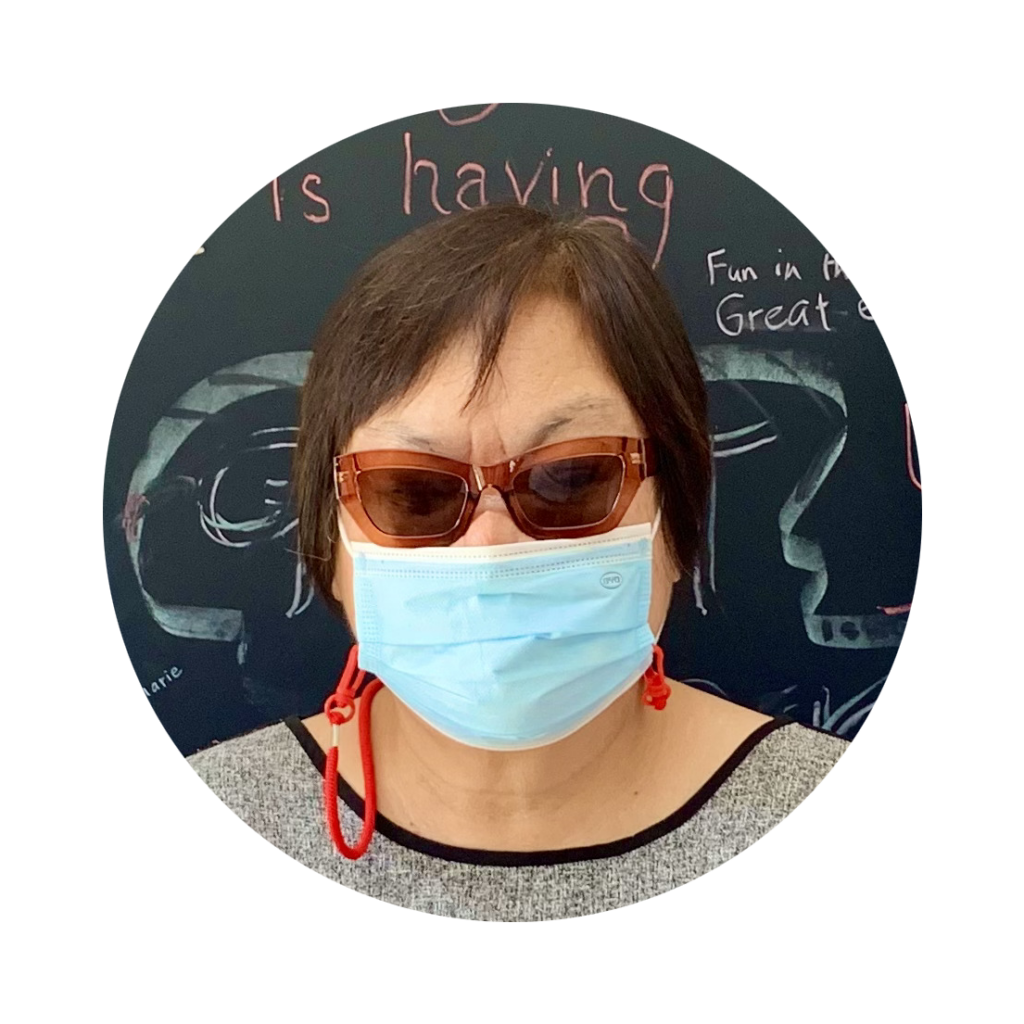
はい、全盲になってから白杖を使い始めました。意外なことに、ロービジョンのときには怖くて外出することが少なかったのですが、全盲になってから目の前に何があっても気にしないと思うようになりました。すると、外出への怖さがなくなり、1人で海外旅行をするまでになったのです。来月はマレーシアのクアラルンプールに1人で旅行します。
ーとても活発に活動されているのですね。皆さん、趣味はありますか?
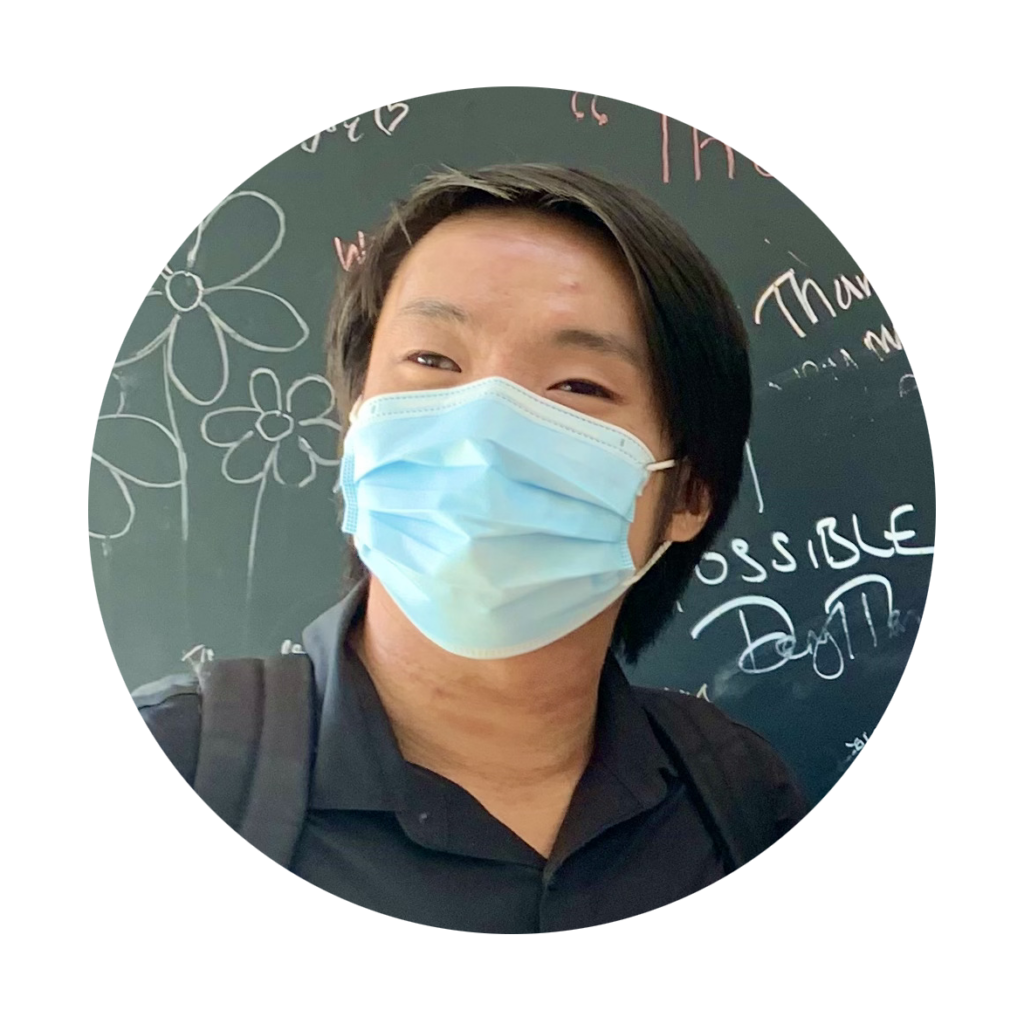
私の趣味は、オーディオ製品を集めることです。たまに、ショッピングセンターへ行って、自分では買えないような、値段の高いヘッドホンを試してみています。
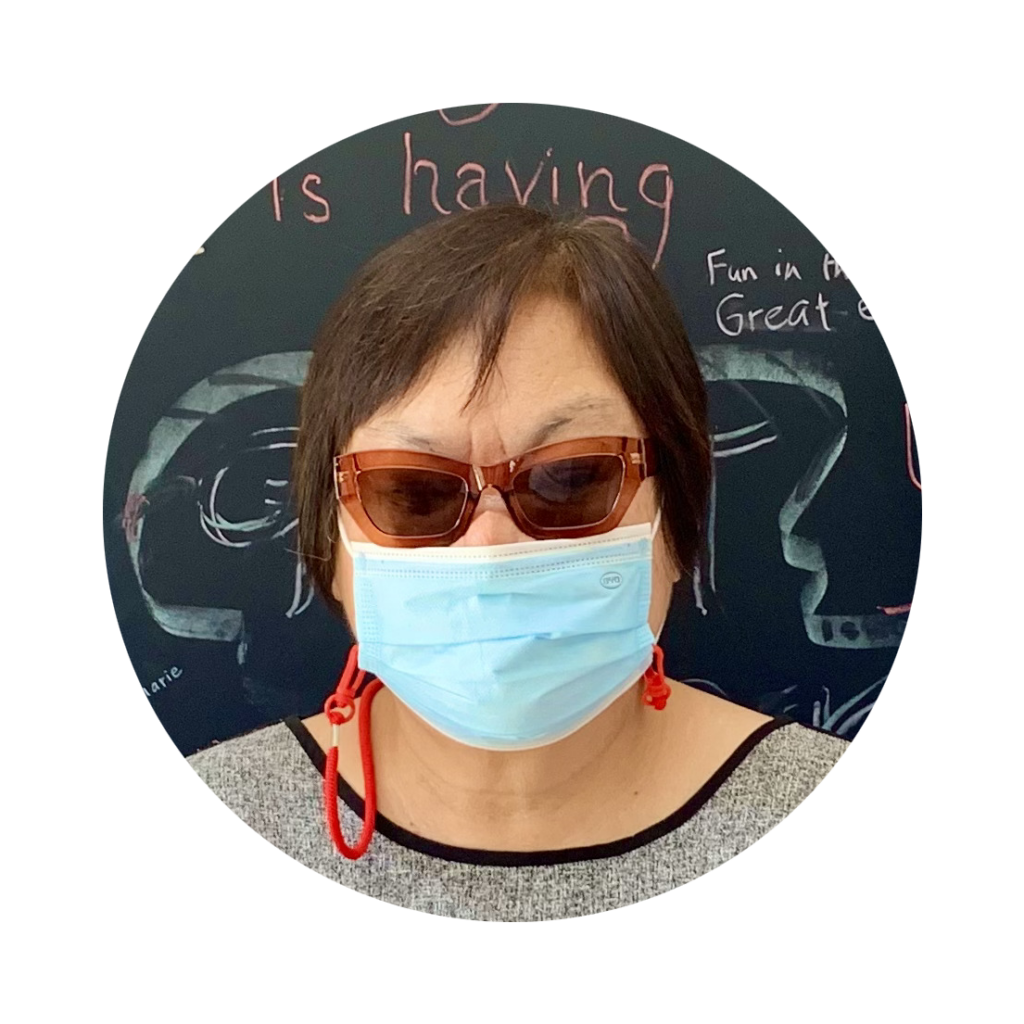
私は、身体を動かすレクリエーションが大好きです。しかし、マラソンをするには自分の速度に合わせて走ってくれる伴走者を見つけるのが大変です。一方、スイミングはプールの場所のイメージができれば1人でできるので、おすすめです。日本に行った際は、スキーのイベントにも参加しました。シンガポールは雪が降らないので1人で練習はできませんが、またいつか雪の上でスキーをするのが夢です。さらに、シンガポールの全盲の視覚障害者がボーリング活動を始めました。その活動が広がり、2002年には、東京で大会を行うために招待されました。今は世界大会も開かれるような規模になっています。

まとめ
シンガポールでは、新しいものを積極的に受け入れようという姿勢を強く感じました。
まず「面白そう」「どんなものか1度体験したい」と関心を持って話を聞いたあと、「具体的にこの場面ではどうなりますか?」「実際に導入するにはこんな課題がありそうです」「この機関に問い合わせるといいですよ」という具体的なアドバイスをいただけます。
「関心を持ってから、現実的な方法を考える」という姿勢は、私たち日本人がつい忘れがちになってしまう点ではないでしょうか。
今回得られた気づきを活かして、今後はぜひ具体的な取り組みをシンガポールで企画していきたいです。そして、シンガポールだけではなく世界の視覚障害者のQOL向上に寄与することで、TomoWorkをはじめ、今回ご協力頂いた皆様に恩返しができるよう、これからも各社の取り組みを進めていきたいと思います。
(記事内写真撮影:Spotlite)※注釈のあるものを除く
編集協力:株式会社ペリュトン