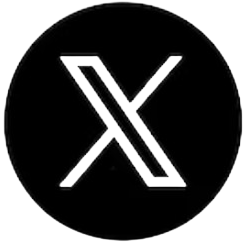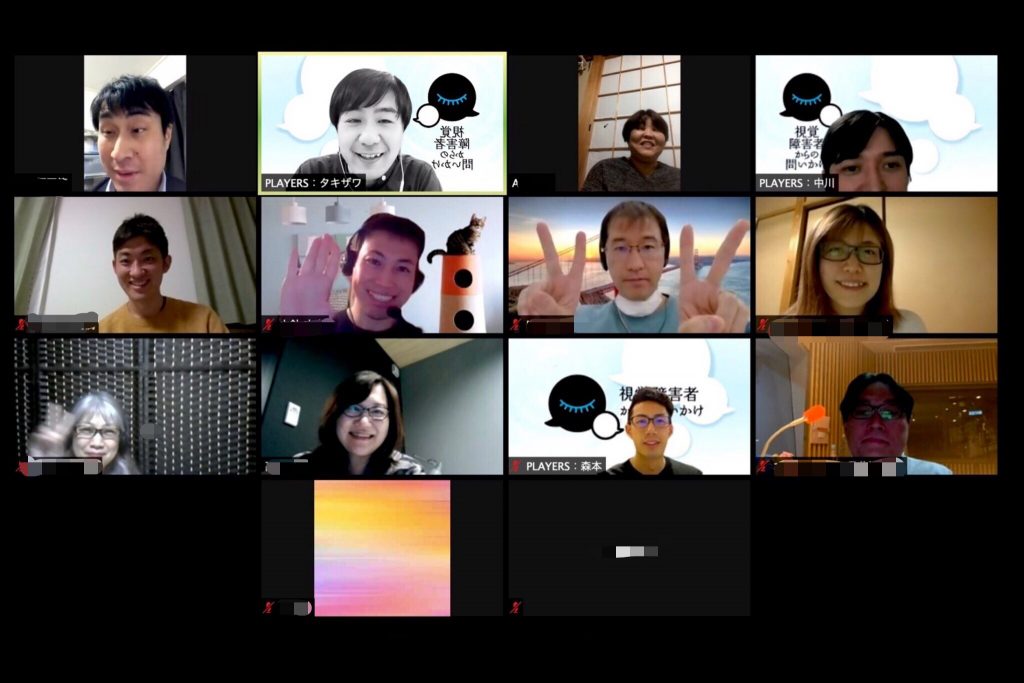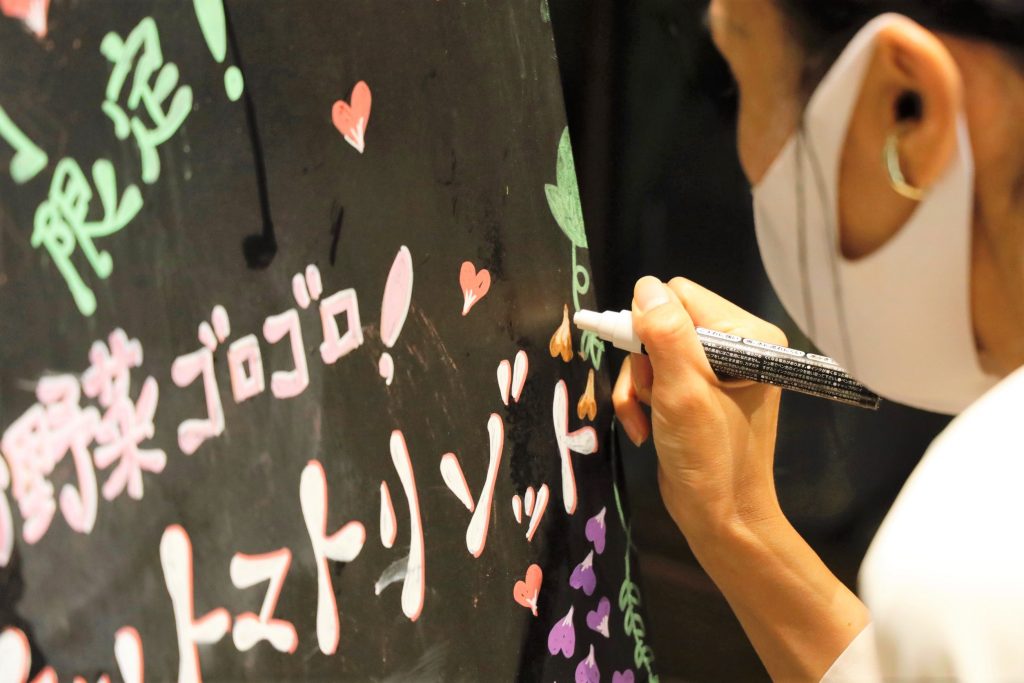「それ、親ガチャでしょ」
10代や20代の若者たちが、そんな言葉を発しているのを耳にする機会が増えました。
「親ガチャ」とは、スマホゲームでアイテムをランダムに引く「ガチャ」になぞらえて、「どんな親のもとに生まれるかは運次第」という、ある種の諦めを含んだ新語です。
他にも、「先生ガチャ」「上司ガチャ」など、自分たちの力ではどうしようもない環境を形容する「◯◯ガチャ」は存在しています。
私は視覚障害者に関わる福祉事業を行う中で、「自治体ガチャ」を感じる機会が増えています。
どの自治体に住むかによって受けられる福祉サービスに大きな差があり、まるで運任せで生活環境が決まってしまうような気がするのです。さらに、福祉だけではなく、医療、教育、子育て支援、防災など、さまざまな分野で自治体によってサービスの質や量、対応の柔軟さに大きなばらつきがあるのが実情です。
今回は、私たちが関わる視覚障害者の同行援護を中心に、自治体ガチャについて考えてみます。
※当記事は、あくまで過去の経験を元にした高橋個人の感想であり、会社としての見解ではございません。また、特定の自治体や担当者の対応を否定するものではありません。
「同行援護」の説明については、以下の記事をお読みください。
「同行援護」の運用主体は国ではなく自治体

視覚障害者の外出時にガイドヘルパーを派遣する「同行援護」は、国が定める障害者総合支援法に基づき運営される福祉制度です。国が定めた制度ですが、運用は各自治体に任されている部分が大きいため、支援内容には自治体ごとの差が出ているのです。
例えば、同じ障害の等級でも、ある自治体では毎月十分な支給量があり、必要なときに何度でもガイドヘルパーを利用できるのに対し、別の自治体では1ヶ月に上限30時間という制限があったり、目的によって対象外だったりと、利用が制限されることもあります。
また、制度そのものは利用できるものの、対応手順の違いによって申請から利用開始までの期間にも差があります。最短1〜2週間で利用できる自治体もあれば、数ヶ月から、長いときには半年ほど時間を要する自治体もあります。これは、「自治体ガチャ」と感じても仕方のない状況ではないでしょうか。
参考:障害者総合支援法が施行されました |厚生労働省(外部リンク)
同行援護の利用の流れについては、以下の記事からお読みいただけます。
要望を伝えたとき、自治体によって対応に差がある
「自治体ガチャ」の現状を、具体的に見ていきます。最大の課題は、支給時間数の違いです。
同行援護は、利用者ごとに1ヶ月に利用できる時間数が決まっています。その範囲内で、利用者は時間数をやりくりしながら事業所に依頼をして、ガイドヘルパーと外出するのです。
そもそも、障害福祉サービスは個別給付とも呼ばれ、本来は個々のニーズや生活状況に応じて必要なサービスが支給決定されます。
一方、自治体では、支給時間の上限の目安となる時間数があります。この時間数の上限は自治体ごとに異なります。非常にざっくりとした個人的な所感ですが、地方の自治体の場合、月に30から40時間程度、首都圏では40から60時間程度を上限としている印象です。自治体の予算や財政への影響などを考慮しているのかもしれません。

上限時間に差がある問題は一旦脇に置き、様々な理由で「上限時間以上の時間を支給して欲しい」と要望した際の自治体の対応が大きく異なるのです。私の経験から、大きく以下の3パターンに分かれます。
- 断固拒否型
「上限時間が設定されており、それ以上の支給はできません」と、どれほど要望しても頑なに断る。 - 条件合致型
「上限時間を超えるには要件があり、その条件に合致すれば支給します」と、条件を提示する。 - 柔軟対応型
「上限時間は目安として存在するものの、1人ひとりの状況に応じて決定するので、まずは詳細を教えて下さい」と、個別対応をする。
私は、理想的なのは3つ目の柔軟対応型だと思います。ですが、断固拒否型や条件合致型の自治体がまだまだ存在します。感覚的には半数以上、7~8割ほどが断固拒否型か条件合致型です。
ある利用者は「自分の区では希望の時間数を支給されなかったが、道路を1本隔てた隣の区に住む友人は、私より多い時間数が支給されている」と嘆いていました。
東京23区の中で、私が比較的「アタリ」の自治体だと感じるのは、新宿区、練馬区、大田区などです。制度の範囲内でできる限り柔軟に解釈してくれたり、親身に対応してくれる姿勢が見えたり、自治体の判断ひとつで支援の質が変わることを感じます。
一方で、「ハズレ」と感じてしまう自治体は、板橋区、世田谷区、江戸川区などです。判断の根拠が不十分だったり、「前例がないから」「区の規定だから」と、納得できる説明もなく門前払いのような対応を受けたりすることがあります。
ただ、このアタリハズレは同行援護の利用に限った感想であり、最近始まった同行援護とは別の新制度は、大田区で実施していない一方、世田谷区では実施しているなど、どの側面から見るかかによって、全く異なります。
私の個人的な感覚だけで、あえて具体的な自治体名を明記したのは、違いがリアルに存在することを知ってほしいからです。これはあくまで一例で、数ヶ月から1年以上前の情報も含まれています。現在は異なるかもしれませんので、噂程度にとらえてください。
もちろん、自治体ごとの規定やこれまでの背景があり、福祉以外の制度なども考慮すると、自治体そのものの評価に直結するわけではありません。しかし、同じ東京都であっても、視覚障害者が「隣の区に住んでいればもっと自由に外出できていたかもしれない」と感じてしまう格差があるのは事実です。
「住みたい街ランキング」「住みやすい自治体ランキング」という言葉をよく目にします。「視覚障害者向けオススメ自治体ベスト10」を独自に発表してみようかな……と思わないこともないですが、いきなりネットで公開するとプチ炎上しそうなので、気になる方は個別にご連絡をください。
多くの視覚障害者は、簡単に自治体を選べない

「それなら、住む場所を選べばいいじゃないか」と思う方もいるかもしれません。しかし、なかなか簡単なことではありません。視覚障害者は、学校や職場への通学通勤のルートが変更になったり、通い慣れた病院やスーパーなどの周辺環境を覚え直したり、生活圏を変えることは晴眼者以上に負担が大きいのです。
さらに、賃貸物件の場合、視覚障害を理由に入居を断られるなど、引っ越し自体が難しいという現実もあるのです。結果として、「たまたまその自治体に生まれた」「たまたまその街に住んでいる」だけで、支援の質に差が出てしまう。この不公平さは、個人の努力だけでは埋めがたいものになっていくのです。
視覚障害者の引っ越しについては、以下の記事からお読みいただけます。
福祉事業者である私たちができること。
では、自治体ガチャが存在する状況で、私たち事業者にできることは何でしょうか。
ひとつは、自治体ごとの制度や運用の違いを把握し、利用者に正確な情報を届けることです。また、制度の説明だけでなく、「こういうケースではこう交渉すれば認められた」という具体的な事例を共有することで、利用者の選択肢を広げることができます。自治体の担当者は、数年で部署を異動しており、制度の理解が不十分な場合が多々あります。私たちから、丁寧に、分かりやすく要望を伝えていくという意識は欠かせません。
また、複数の自治体の事業者や行政関係者などとのネットワークを築くことも重要です。自治体をまたいだ連携があれば、制度の違いによる壁を少しでも越えることができます。
実際にこんな事例がありました。京都府内のある自治体で認められていた利用方法を、別の視覚障害者が神奈川県内の自治体に相談すると、最初は「利用できない」と回答をもらったことがありました。
しかし、私たちが間に入り、「京都の◯◯市では利用できている。担当者同士で連絡して、確認いただけないか」と伝えると、実際に神奈川の担当者が京都の担当者に連絡を取ってくださり、最終的には利用が認められたケースもあります。
さらには、利用者の実際の声を行政に届ける役割も重要です。現場での困りごとや希望を具体的な数字や事例としてまとめ、議員や様々な業界団体などを通して行政に提言していくことが、改善の第一歩になるかもしれません。
ガチャではなく「希望する支援が受けられる社会」に近づくために
「自治体ガチャ」という言葉には、諦めのニュアンスが込められています。しかし、本当に目指すべきは、どこに住んでいても、誰であっても、必要な支援が受けられる社会です。
今の現状から、すぐに実現することは難しいかもしれません。だからと言って、現状を嘆き柔軟な自治体を羨むだけで、何もしないのは無責任です。現場の違和感を無視せず、課題として共有し、少しずつでも改善に向けた動きを重ねていくことで、ガチャではなく希望する支援が受けられる社会に近づけるのではないでしょうか。
福祉サービスが、運まかせではなく、納得のいく仕組みとして提供される。そんな未来のために、私たちも日々の現場から声をあげていきたいと思います。

記事内写真撮影:Spotlite
編集協力:株式会社ペリュトン