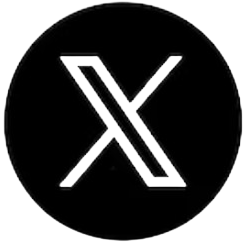最近友人が、同行援護従業者の資格を取得しました。「依頼が来たものの受けようか迷っている」と話す彼女に、「どんなことが不安?」と聞いてみたところ、次のようなことを口にしていました。
「利用者さんを怪我させてしまったら、などと考えて一歩目が踏み出せない」
「最初はどんな依頼から受けるべきか」
「ガイドをしている最中、どんな会話をすればいいのだろう」
「混雑時の電車やエスカレーターの乗り降りで失敗したらどうしよう」
実は私も同行援護の仕事を始める前、全く同じような不安を抱えていました。そこで今回は、私がどのようにして最初の一歩を踏み出せたのか、当日の様子、そして実際にガイドをしてみて気づいた反省点などを、できるだけ具体的にお伝えしたいと思います。

白石さんがガイドヘルパーの資格を取ったときの体験談は、以下のリンクからお読みいただけます。
「初稼働のヘルパーでもOK」な案件に挑戦
同行援護事業所みつきの場合、同行援護の依頼は、LINEで送られてきます。
利用者さんの年齢や性別、予約希望日時、お出かけの内容などの詳細をチェックし、対応できそうなら「受ける」をタップ。これで利用者とヘルパーのマッチングが完了します。
私は今回、「初稼働のヘルパーでもOK」という依頼を受諾。20代の大学院生Aさんとメキシコ料理を食べに行きました。Aさんの最寄り駅まで迎えに行き、電車で移動してランチをする流れです。
実は、これまでにも何度か依頼が来ていたのですが、「自分に務まるだろうか」という不安から見送ってきました。そのため「初めての方でもいいよ!」と言ってくださる利用者さんがいてくれるのは、とてもありがたいことです。
また、ガイドヘルパーの先輩たちが「とにかく現場に出てみることが大切」と後押ししてくれたことも、大きな励みになりました。
当日は、電車の遅延や乗り間違えも考慮して早めに家を出たため、待ち合わせ時刻の15分前には到着することができました。
しかし電車を降りて待ち合わせ場所である改札に向かう最中、私の頭の中は「どうしよう、大丈夫かな」という思いでいっぱいに。平日の昼間なのに、電車が混んでいたからです。
資格取得の講習で電車の乗降などの練習はしましたが、空いている時間帯に行われたため、難しくはありませんでした。しかし、実際のお出かけではそうはいきません。スムーズに行動できるよう、頭の中でシミュレーションを繰り返しました。
スタート早々の反省

待ち合わせ時間ぴったりに白杖を持った男性が現れたので、私は「こんにちは。Aさんですか?」と声をかけ、自己紹介をしました。
Aさんはまず、「券売機でヘルパー用のICカードにチャージをしたい」と言いました。「自分でできるので大丈夫ですよ」とのことだったので、斜め後ろで待機します。
チャージが終わったので、「どちら側でガイドすればいいですか?」と確認。私はAさんの左側について歩き始めました。
ICカードをお借りして改札を通るとき、私は講習で習ったようにAさんの前に出て、後ろに回した手に掴まってもらう形で進みました。
しかしその後Aさんから、こうフィードバックをもらいます。
「ヘルパーが先に行くと、改札をうまく通れなかった利用者がひとり取り残されてしまうことがあります。ですから、同行援護事業所みつきでは利用者が先に行くことになっているんですよ」
※事業所によって異なる場合があります。今回はみつきで推奨している誘導方法の話であることをご理解ください。
幸い今回は無事に改札を通過できましたが、「前を歩いていいですか?」と事前に確認していればよかった……と、スタート早々の反省です。
混雑した電車で2度めの反省
ホームに続く階段をAさんとのぼっているとき、私は講習で先生に言われたことを思い出していました。
「多くの利用者さんは、あなたたちが思ってるよりもずっとスタスタと歩くよ」
まさにその通りでした。講習では、アイマスクをしたペアをガイドする練習をしましたが、参加者はガイド役の腕をガッチリと掴み、おそるおそる歩きます。ガイドをする側も、「しっかりと支えなければ」と緊張するのです。
そのためAさんの歩くスピードと足どりの軽やかさに驚きつつ、緊張が薄れていくのを感じました。
ホームで電車を待ちます。目的地まで乗り換えはなく、乗車時間は24分。到着した電車のドアが開くと、予想通り車内は混雑していました。私たちが乗れるスペースはありましたが、乗り込むのが精一杯で、手すりや座席の近くには行けません。Aさんの隣に立つこともできず、どうサポートするのが正解なのか迷ってしまい、「大丈夫ですか?」と声をかけることしかできませんでした。
Aさんは「大丈夫です」と言うと、上に手を伸ばして吊り革を探し、掴みました。その姿を見て私は、吊り革の位置をお伝えしなかったことに気づきました。2度目の反省です。
次の駅で手すりのある角のスペースが空いたので、「角に移動しますか?」と確認してから移動しました。ようやくここで落ち着いてAさんとお話ができるようになりました。

おいしいご飯を食べるのが好きなAさん。同行援護を利用して、気になる飲食店によく足を運ぶそうです。
「店内の構造や注文方法がわからないので、初めて行く店にはヘルパーさんについてきてもらうことが多いです。そうしたら、2回目からは自分でいけるので」
前回は、ヘルパーさんと「ラーメンを食べに行った」といいます。ラーメン屋は食券を買わなければいけないので、ひとりで行くのは難しいのだと教えてくれました。
初めてくる街だと思い込んでいた私
目的地の駅につき、階段を降りて改札に向かいます。窓口で障害者手帳を提示し、割引を受けてから改札を抜けました。忘れないうちにICカードをAさんにお返しします。
人通りの少ない場所で一度立ち止まり、「Googleマップを開くので待っていただいてもいいですか?」と声をかけ、目的地の方向を確認してから歩き始めました。
広い道を直進しながら「周囲に何があるか説明しますか?」と聞くと、「実はこの駅でアルバイトをしているので、このあたりのことは知っています。目的地のビルについたら、中にどんな飲食店が入っているかなどを教えてもらえますか」と答えてくれました。
私は、Aさんが初めて訪れる街だと勝手に思い込んでいました。また講習で「移動中は周囲の景色を伝える」と教わったことにとらわれすぎていたようです。Aさんははっきりと意思表示してくれましたが、気を遣ってそうできない人もいるはずです。
次回からは、「この街にくるのは初めてですか?」と聞いてみようと思いました。なんでも質問すればいいわけではありませんが、相手の暮らしを想像した上でのコミュニケーションが大切なのだと感じたのです。
目的地まで歩きながら、映画好きのAさんからおすすめの作品を教えてもらったり、私が最近観た映画をシェアしたりしました。
10分ほどでビルに到着し、「先に他の飲食店を見てみますか?」と確認したところ、「食事のあとで大丈夫です」とのことだったので、エスカレーターで3階にある店に向かいました。
しかし、3階のフロアを見渡しても目的の店が見つかりません。「フロアマップでは、ここのはずなのに……」と焦ります。
歩き回らせるのは申し訳ないので、Aさんには壁際で待ってもらい、向かいにあったコーヒーショップで場所を尋ねました。「この先の出入り口から一度外に出てください」と案内され、改めて店に向かいます。
メニュー選びは「カテゴリ」で

ガラス張りの明るい店内。広さはあったのですが、通路はギリギリひとりが通れる程度だったので、私が前を歩きます。案内された二人席は、片側が椅子、もう片側がソファでした。Aさんの手をとり、椅子の背もたれを確認してもらい着席します。
続いてメニュー選びです。メニューには約9種類のメキシコ料理が並んでいました。
実は、私が、講習でいちばん難しいと感じたのがメニューの説明でした。メニューには多くの情報が含まれているため、効率的な情報提供が必要です。さらに、情報提供だけではなく「食べたい」と思ってもらえる言葉選びも必要だと教わりました。
また当事者の方から、「早く決めなきゃと気を遣うことがある」と聞いたこともあったので、自分のペースで選んでもらえることを意識します。
まず「タコス系と、バーガー系、肉料理系があります」とカテゴリでお伝えしました。
それに対し、Aさんが質問を重ねてくれます。
「肉料理はどんなものですか?」
「パンやライスはつきますか?」
メニューの写真を参考に、肉のボリュームや付け合わせの野菜などもお伝えします。ドリンクメニューは「オルチャタ」「タマリンド」といった聞き慣れないものも多く、スマホで調べながら説明しました。
情報提供の難しさを痛感
Aさんはグリルポーク、私はタコスを注文。料理がきたら、料理と飲み物の位置をお伝えします。しかし私はここでも、情報提供を失念してしまいました。
お肉がどんな形状になっているかを伝えないまま、フォークとナイフを渡してしまったのです。
Aさんは、「グリルポーク」を切り分けられていない大きな肉だと思ったのかもしれません。ナイフで切ろうとするもうまくフィットせず、「お肉ってどんな感じですか?」と私に聞きました。その時になって、私は自分の情報提供が不十分だったことに気づきました。

「すみません、ステーキのように縦長に切ってあります」とお伝えすると、「それならかぶりついた方が良さそうですね」と、フォークのみを使って食べ始めました。
いかに自分の「当たり前」を軸にコミュニケーションをとっているのかを痛感しました。
ふと、講習での先生のお話を思い出しました。視覚障害者と晴眼者をライブビデオでつなぐ無料アプリ『Be My Eyes』を使用した際のエピソードです。
「依頼主は中年の男性で、『箱の中に本を並べたい』という一見すると簡単な依頼でした。私は情報提供に慣れていたので、本のタイトルや向きをお伝えして無事並べ終えましたが、その方は『あなたで4人めだった。やっとできました』と言っていました。それほど、必要な情報を正しく伝えるのは難しいことなのです」

私の不安は「知らなさ」からくるものだった
食事中は、Aさんのが海外留学時代の思い出や、同行援護を利用して大阪へ旅行した際の話を聞きました。特に印象に残っているのは、作家の高野秀行さんについての会話です。
「アメリカに行く飛行機のなかで、高野さんの『語学の天才まで1億光年』を読んで勇気づけられた。でも実際はそんなにうまくいかなかったけれど」と笑いながら教えてくれました。
個別会計ができない店だったので、「私がまとめて支払ってもいいですか?」とAさんに確認し、あとから現金をいただくことに。
店を出て、Aさんの希望どおり1〜2階の飲食店を見て回りました。巡りながら「メニュー」「金額」「混雑具合」「客層」を中心にお伝えしましたが、振り返ると「店内の広さ」「券売機の有無」「カウンターかテーブル席か」といった情報もお伝えするべきだったと考えています。
巡り終え、駅に向かいます。別れ際、Aさんが言ってくださった「楽しかったです。ガイドお上手でした」という言葉が心に残っています。
こうして3時間におよぶ初めてのガイドが終了しました。
振り返ると反省点が多々ありますが、最後にもうひとつ反省があります。
それは、必要以上に「サポートしなければ」と気負いすぎていたことです。Aさんと過ごすなかで、私が抱いていた不安は「知らなさ」からきていたと気づきました。だから私は、Aさんが階段をのぼるスピードを実際に「知った」とき、緊張がほぐれたのだと思います。
もちろん利用者さんは料金を支払ってサービスを利用しているので、私はこれからもしっかりとスキルを磨かなくてはなりません。ただ、必要以上に不安を感じたり気負ったりしているのであれば、一度チャレンジしてみてほしいと思うのです。
それは、普段食べないメキシコ料理がとてもおいしかったこと、「ニューヨークのハーレムで食べたご飯が最高だった」と留学時の思い出を教えてもらえたこと、この機会がなければ出会うことがなかったAさんの経験をほんの少しシェアしてもらえたこと。これらが自分にとって、とても楽しく、貴重な時間だったからです。ごく個人的なひとつの考えとして受け取ってもらえれば幸いです。
ガイドの依頼を受けようか悩んでいる友人にこれらのことを話すと、彼女は「受けてみる」と言いました。
私や彼女のように、「資格をとったはいいものの一歩踏み出せない」と悩んでいる方、ガイドヘルパーに興味のある方にこの記事が届き、「私にもできそう」と思ってもらえることを願っています。
Spotliteを運営している株式会社mitsukiでは、ガイドヘルパーを募集しています。
詳しくは以下のページをご確認ください。
アイキャッチ写真撮影:Spotlite
執筆:白石果林
編集協力:株式会社ペリュトン