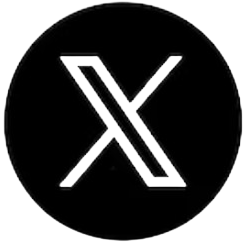2024年7月中旬、私は「同行援護従業者養成研修」を受ける予定でいました。
この研修は、ガイドヘルパーとして視覚障害者の同行援護に従事するために、受講必須なものです。
私はSpotlite編集部の一員として、数年間、視覚障害者や支援者、専門家の方々と関わってきました。Spotlite編集長で株式会社mitsuki代表の高橋さんから「ガイドヘルパーの資格を取ってみませんか?」と誘われたのがきっかけで、受講を決意しました。
しかし、研修の1カ月前の6月、私の夫は救急搬送されました。
研修を受けるか否か
「俺の入院に関係なく、予定していた研修は受けてね」
夫が緊急入院した翌日にはそう言われたのを、一年以上経った今でも覚えています。
のちに、検査で肺腺ガンのステージ4であったとわかりました。在宅勤務で仕事を続けていた夫の具合が日に日に悪くなり、予定していた検査入院を前倒しして緊急入院することになりました。
入院した安心感や、強い痛み止めの投与開始のおかげで、入院直後の夫は少しだけ元気になったように見えました。しかし、ガンの種類もその時点では特定できておらず、すぐには治療に取り掛かれませんでした。

私は、院内にあった、ガン患者とその家族が相談できる支援室に行き、支援制度などの相談をしました。
また、以前から予約していた同行援護の研修を受けるかどうか悩んでいました。「7月の中旬に同行援護従業者養成研修を受ける予定だが、キャンセルしなくていいだろうか」と相談をしたところ、「その時期までに退院はしないと思います。資格を取るならむしろ入院中に受けておいた方がいい。介護が始まったら受講の機会は遠のいてしまうだろう」とのことでした。入院直後で、医師と看護師も、私たち家族も「一度退院して介護制度を活用しながら外来でガン治療をする」という方向で考えていた頃でした。
私は、mitsukiの高橋さんと編集部の一部メンバーに状況を共有し、研修はキャンセルする可能性もあるが、できれば予定通り受講したいと伝えました。皆さん理解をしてくださいました。
しかし、担当医師も予想できなかったほどに病の進行は早く、今思えばあらゆる面で夫は回復には向かっていませんでした。
病床で親指を立ててグッドサイン。資格取得を喜んでくれた夫
入院から約1カ月、研修の直前に、夫は「積極的な治療はしないで、緩和ケアに移行したい」と決断しました。
症状が進行し、かなり苦しくつらかったのだと思います。治療のための体力回復は見込めなくなってきていました。家族全員、涙を流しながら夫の意志を尊重する決断をしました。緩和ケア専門の病院へ転院しようと、義理の姉とともに動き始めました。
その週末、私は研修を受けてくると夫に伝え、姉に夫の付き添いを依頼しました。
研修は都内のターミナル駅。時期は7月の中旬。地下鉄での列車乗降研修も、屋外での階段研修も、とても暑かったのを覚えています。研修中は目の前のことに集中し、私は束の間、夫の病のことを考えないでいる時間を過ごしました。
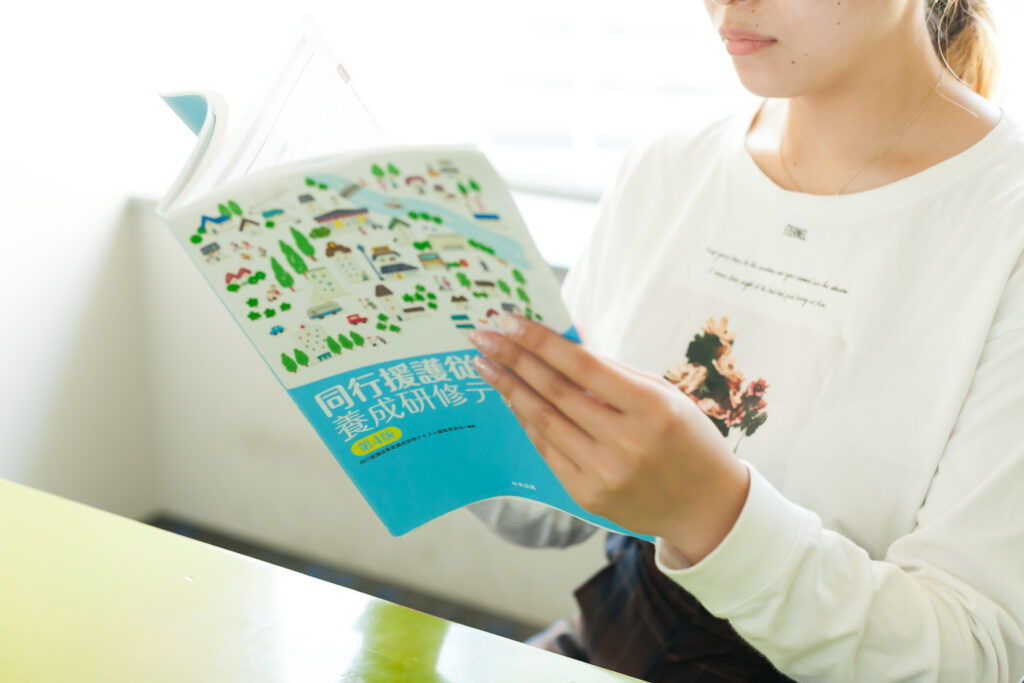
対面の実習は朝から夕方まで2日間あり、病院の面会時間には間に合いませんでした。地下鉄で帰宅するとき、入院していた病院の最寄り駅を通るので、そのタイミングで祈る気持ちとともに、ハートや応援のLINEスタンプを夫にいくつも送りました。
この週末から、夫は痛みを強く訴え、痛み止めの投与方法や量が変わりました。研修1日目の夜に、薬の影響による幻覚や幻聴が原因と思われる意味不明なLINEメッセージがきたり、パニック状態の電話がかかってきたりしていました。
週が明けて面会に行くと、もうほとんど話す事ができず、酸素マスクは大きなものに付け替えられ、呼吸もものすごく荒くなった夫がベッドにいました。
それでも「同行援護従業者の資格が取れたよ」というと、力強く親指を挙げてグッドサインで喜んでくれた様子が、今もはっきりと目に浮かびます。
その2日後、緩和ケアの病院に転院することなく、夫は亡くなりました。57歳でした。
夫のそばにいなかった後悔を変えた、「不登校支援」と「視覚障害者支援」
それ以来、私はずっと「なぜあの日、研修をキャンセルしなかったのか」と後悔をしていました。
当時、私たちの子どもは高校生。世帯主である夫が亡くなり、行政や民間の手続きがたくさんありました。
ガイドヘルパーの仕事はおろか、もとからやっていた仕事もセーブをする日々が続きました。数カ月たって、従来の仕事は少しずつ復帰しましたが、夫の死の記憶とガイドヘルパーの資格は強く結びついてしまい、登録して稼働する気持ちにはなれずにいました。

それから半年以上経った頃だったと思います。偶然の出来事がありました。
夫と私は「不登校の親の会」を手伝っていました。特に夫は熱心で、事務局の一員として行政とのパイプを模索したり、ほかの方が主催する別の「親の会」に、関東圏はもちろん、つてがあった九州の会にも参加したりするほどでした。夫は「仕事以外のライフワークを見つけた」と言っていました。入院することになったとき、この活動を自分が中断することは「心残りだ」と話していました。
その不登校の親の会に、ある視覚障害者の方から「参加したい」とメールで問い合わせがありました。
そのとき、すべてがつながったような気がしたのです。勝手に「これは何かの運命だ」と感じました。全国に約40万人いる不登校の子どもや保護者の中には、当然、視覚障害者もいるでしょうし、ほかの障害がある場合もある……そんな当たり前のことに気づきました。夫が大事にしていた「不登校の親の会」と、私が関わっていた「視覚障害者の支援」がつながった瞬間でした。
結局その方は都合がつかなくなり、会に参加することはありませんでしたが、私の同行援護従業者の資格が、不登校支援の場でも役に立つかもしれないという気づきは大きいものでした。この出来事をきっかけに、ゆっくりと段階を踏みながら私の気持ちは整理されていきました。夫を思い出すからと休んでいた「不登校の親の会」のサポートも復帰し、Spotlite編集部の仕事にもより深くかかわることが増えていきました。
そして、夫が亡くなってから10カ月ほど経過したころ、私はガイドヘルパーとして「みつき」に登録しました。
ヘルパーとしての初稼働
しかし、登録してから実際に稼働するまで、私も多くのヘルパーさんと同様、依頼を何回も見送りました。
LINEのメッセージから、「おでかけくん」で詳細を確認するけれど「見送る」ボタンを押す。どうしても時間が合わなかったり、不安で迷っているうちに他のヘルパーさんに確定していたり……そんな状態が3カ月ほど続きました。
ある日、とある依頼が目に留まりました。利用者さんが仕事を終えてから、自宅の最寄り駅周辺で日常生活の視覚情報などをサポートする依頼でした。夕方から夜の依頼でしたが、時間もそれほど長くなく、他の業務にも影響が少ない。
私にとって、日常生活での支援は何をするかイメージしやすいものでした。依頼を受けたい気持ちが高まりました。研修でやった内容と似ていたことや、研修のときに私がロールプレイングでほめられた内容が依頼の中に入っていたのも、安心感につながりました。
数日迷って「依頼を受ける」のボタンを押しました。
依頼を受ける少し前に、「みつきエキスポ」の取材を担当したことも大きかったように思います。いろいろな視覚障害者が自分を表現し、楽しんでいる。それを実際にこの目でみたことで、視覚障害者やガイドの仕事に対する心理的な距離感が、さらに近づいた気がします。
はじめての同行援護を終えて帰宅するとき、研修後と帰宅経路が同じであることに気づきました。地下鉄で夫が亡くなった病院の最寄り駅を通るとき、その日はつらくなりませんでした。ガイドヘルパーの仕事と夫の記憶は、私の中で少しずつ切り離されてきた……そんな風に感じました。
違う誰かの人生と出会う、同行援護の仕事
人はみんな違います。視覚障害者も、それぞれ見え方も好きなことも得意なことも違います。
みつきのガイドヘルパーにもいろいろな方がいます。学生さんもいます。副業としてガイドヘルパーを始める方もいます。ガイドと関係がないと思っていた特技が、みつきのイベントにつながった方もいました。
そして、私のような葛藤を経験したガイドヘルパーもいます。
相性もあるでしょうし、ガイドの経験によって技術の差もあるでしょう。経験による差は、みつき全体でもスキルアップに取り組んでいます。
違う人生を生きている誰かと出会い、同行援護を通してその方の生活の一部を知っていく。それが同行援護の魅力だと、私は感じています。
執筆:aki
記事内写真撮影:Spotllite(※注釈のあるものを除く)
編集協力:株式会社ペリュトン