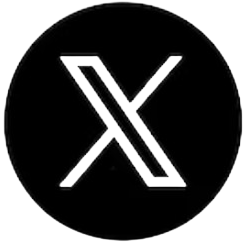魚を三枚におろして料理をする。視覚障害があってもそんなことできるの?
普段から自炊をしている私ですが、正直なところ「難しそう」というイメージがありました。でも、だからこそ挑戦したくなるのが、好奇心旺盛な私です。今回、視覚障害者向けに開催された料理イベントを、全盲のライターがレポートします。
魚を手で触って、その感触や骨に包丁が当たる音を頼りに進める調理は、まさに五感を使った発見だらけの体験でした。
野菜を切る音やちくわの感触。視覚に頼らない調理のおもしろさ
まずは、包丁の練習からスタートです。
最初の練習は、ちくわや小松菜を切ること。視覚に頼らず、包丁の動きを手で感じながら慎重に切っていきます。今回のイベントでは、視覚障害の小学生も参加していました。小松菜の束がばらばらになってしまったり、にんじんが硬すぎたりして、子どもたちは苦戦しています。ですが、「サクッ」という小松菜を切る音や、ちくわのやわらかい感触を楽しみながら調理を進めていきました。

次に、ピーマンの種取りから魚の内臓処理の練習へ。
魚の内臓を取り出すための練習として、ピーマンの中に手を入れて種を取り除く作業を行いました。手で探って種をかき出すと、出しても出しても種が出てきてしまい、みなさんもなかなか苦戦していた様子でしたが、根気強く最後まできれいにしていました。私も、ここまで来ると、いよいよ次の魚さばきが楽しみになってきます。
アジの三枚おろしに挑戦。「この音が聞こえると成功なんだね!」

いよいよアジが登場!手で触ってみると、ヌルッとした独特の感触が新鮮で、小学生たちは触りなれない感覚に声を上げて驚いていました。アジの頭から尻尾へ、尻尾から頭へと手を動かすことで、鱗の向きや魚の形を理解した子どもたち。尻尾付近の硬い「ぜいご」と呼ばれる鱗を指でなぞり、その硬さに驚きながら「これ、切り取れるのかな?」と少し不安になっている様子でした。でも、講師からのアドバイスを聞きながら「ぜいご」を包丁で丁寧に切り取り、鱗を落とす作業もスムーズに進みました。

このときに注意しなければいけないことは、シンクで水を流しながら鱗を落とすこと。もしまな板の上でやってしまったら、鱗が飛び散って大変なことになってしまいます。
次はいよいよメインの三枚おろしです。包丁を背骨に沿わせて切るには、「骨に当たるとカリッと音がする」という感覚を大事にすること。包丁を背骨に沿わせて、骨に当てながら切ることで、身を無駄にせずに3枚におろすことができるそうです。私も挑戦してみましたが、1尾目はかなり骨に身が残ってしまいました。小学生たちは「この音が聞こえると成功なんだね!」と、包丁を動かす手にも自信が出てきた様子でした。

美味しい料理が完成!自分たちで作った達成感
三枚におろしたアジに、小麦粉、卵、パン粉をまぶし、油で揚げてアジフライに仕上げます。他にもアラ汁、しじみ汁、野菜炒め、骨せんべい、イワシの煮付けなど、豪華な魚尽くしメニューがずらり。

特に人気だったのはアジフライです。小学生たちは自分たちで手を動かして作った料理に舌鼓を打っていました。
全盲でも魚はさばける。触覚で理解した「命をいただく」こと
私が印象に残った小学生たちの反応がありました。魚の内臓を取り出しているとき、小学生のひとりが「かわいそうだね」とつぶやいていたのです。普段は調理された状態の魚を食べているため、今回捌いてみたことで「命をいただく」という実感が湧いたのかもしれません。その後も「ここがエラなんだね」「これが内蔵か」と魚の構造について興味を持ち、調理に臨んでいました。
そして、私の感想は「全盲でも魚はさばける!」ということ。今回のイベントを通して、魚をさばくことの楽しさを実感しました。一見「難しそう」と思う魚の調理ですが、形の特徴や刃の入れ方を教えてもらったことで、無事に習得ができました。今後は、もっと大きな魚にも挑戦してみたいと思います!

執筆協力:川本一輝
記事内写真撮影:Spotlite
編集協力:株式会社ペリュトン