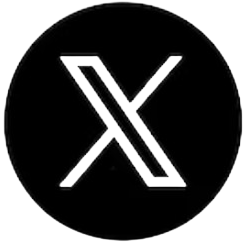横浜市立みなと赤十字病院に眼科部長として勤務する椎野めぐみさん。
昨年より視覚障害者に対するロービジョンケアを本格的に始め、院内での交流会や音楽会、パラアスリートの講演会など様々なイベントを企画しています。
椎野先生の取り組みを前編、後編の2回に分けてご紹介していきます。
前編では、ロービジョンケアを始めたきっかけや眼科医の枠を超えた取り組みの現状、根底にある椎野先生自身の経験をお伝えします。
略歴
神奈川県生まれ。浜松医科大学医学部卒業後、横浜市立大学付属病院等を経て、現在はみなと赤十字病院眼科部長。毎月1回、横浜市立大学ロービジョンケア外来も担当。
2018年上智大学グリーフケア研究所臨床傾聴士を取得。趣味は、美味しいものを食べること、感動する本を読むこと。
インタビュー
手術に一生懸命だった若手時代
ー今のお仕事内容を教えてください。
みなと赤十字病院の眼科で診察をしています。一般外来の診療と白内障の手術が中心です。
毎月1回、横浜市立大学眼科のロービジョン外来で視覚障害のある患者さんの診察も行っています。
ーなぜ、医者になろうと思ったのですか?
小さい頃、親に「将来、人の役に立つ人間になりなさい」とよく言われていました。シュバイツァーや野口英世の伝記を読んだり、マザーテレサのことを知るようになり、人の役に立つためには医者になるのがよいのかなと自然に思うようになっていました。
ー色々な科がある中で、眼科医になろうと思った理由はありますか?
医学生の時、病院実習中に、自分でも意外なことに手術の見学が面白くて血を見るのが嫌いではなかったのです。手術室に入れて、また女性としても長く続けられるのは何だろうと考えて、眼科を選びました。
でも、診療の科にはマイナーとメジャーという分け方があって、循環器科や心臓外科など命に直結する科はメジャー、それに対して皮膚科、眼科、耳鼻科などはマイナーと分けるのです。
眼科はマイナーな科だと思うと、医者の王道ではないのかなと思う気持ちが少しありました。
ーそうなんですね。その気持ちは今はあるのですか?
いえ、ありません。大学卒業直後から眼科を選んでいたのですが、さらに研修医の時、尊敬する上司の先生から「眼科は大切なんだよ。人は死んでしまったらその人の人生が終わるけれど、目が見えなくなってもその人の人生は続くのだから」と言われました。その言葉がとても心に響いて、一生自分は眼科でやっていこうという決意が固まりました。
ー眼科医になられてからはどのようなお仕事をされていたのですか?
最初は手術に一生懸命でした。白内障の手術を中心に、色々な疾患の手術を教わりました。見えるようになると患者さんが喜んでくれるので、やりがいや達成感がありました。上司にも恵まれ、充実していたと思います。しかし、大きな病院の若い医者はだいたい2年ごとに転勤します。だからどうしても治せない患者さんがいても、一人一人の患者さんのその後の人生がどうなるかを長く診ることができなくて、十分に対応できませんでした。

自身の経験を踏まえて、ロービジョンケアの道へ
ーそのような患者さんに意識が向くきっかけはあったのですか?
実はその前から、ロービジョンという分野があって、神奈川県にも視覚障害者のための福祉施設があるのは知っていました。でも「自分は患者さんを手術で治して喜ばれたい」と思っていました。
部長として多忙になる中、私自身が公私ともにいろいろあって、バーンアウトしてしまいました。生まれて初めて静養のために入院して患者の立場になったときに、「患者はその人自身が好きで病気になっているわけじゃない」と感じました。病気になると、突然病人になってしまい、周りも病気に目が行ってしまいますが、本人自身の中では何も変わっていないのです。
そんな時、たまたま手にした最相葉月の「セラピスト」という小説の中で、視覚障害に苦しむ人が心理カウンセリングを受けるという話が出てきて「そういう人もいるんだな」と印象に残りました。
職場に復帰した後、大学で一緒だった清水朋美先生から「パラリンピックのアスリートのクラス分けをみなと赤十字でやってくれないか?」という連絡を頂きました。それで勉強のために視覚障害者用補装具適合判定医師研修会に参加し、ロービジョンケアへの道が始まりました。
ーどのような取り組みを始められたんですか?
まずは、今まで検査と薬の処方だけで終えていた視覚障害の患者さんに対して、県内の福祉施設などを積極的に紹介するようにしました。でも情報を提供しても、なかなか行かない人が多いのです。一人で移動できない、家族の都合がつかないなどの色々な理由があるのですが、病気を認めたくないという気持ちもあるのだなと思いました。
ちょうど同じくらいの時期、ロービジョンに関する学会のメーリングリストで、新潟の安藤先生という方が、毎月1回病院の診療時間外に視覚障害者と話をする会を催していることを知りました。その中の当事者の話に心を動かされました。
「病院だったら患者さんは定期的に来ている。であれば、病院に居場所となる場所を作ろう」というのがロービジョンケアの会をやってみようと思ったきっかけです。

継続すると、嬉しい声が
ー具体的にはどのようなことをされたのですか?
2018年の2月から毎月1回、患者さんが病院の会議室に集まって、お話をしたり、ヨガをして身体を動かす機会を作りました。それとは別に、半年に1回程度、病院の中で音楽の演奏会を行ったり、パラアスリートを招いて一般の方も参加できる講演会を行ったりしています。
ー毎回の集まりではヨガを行われているとのことですが、どのような効果を感じていらっしゃいますか?
目以外の感覚に意識を向けることで、身体を再認識する手段になっているような気がしています。視覚も五感の一つなので、身体とつながっていることを感じることができます。聖書の中に「身体の中でそれぞれ、頭が足に向かってお前馬鹿だ、手が胃袋に向かって何もしてない、などと言うことはない」という話が出てきます。人間関係のことを例えた話だと思いますが、身体それぞれの働きがあってどこかが特別にえらいわけではなく、みんなで協調していくものだと気づきます。
ー患者さんの集まりを行って、何か反響はありましたか?
患者さんはそれぞれ視覚の程度や段階に差があり、一人として同じ方はいません。毎回来たいという人もいれば、1回で来なくなった人もいます。何回か続けていくうちに、嬉しい声もありました。
付き合いの長い患者さんから「見えないと思って諦めていたのに、こういう会があって、先生が楽しいことをしてくれるから、今ここに来ることが生きがいのようになっててすごくうれしい」
別の方は「これまでできていたことが色々できなくなるかと思うとすごく落ち込んでしまう。だけど、私は先生に巡り会ってこうやって話を聞いてくれるから、自分はまだ恵まれてるのかな」と言っていただけました。その方は、私が仕事を休んだ時に心配してくれていた方だったので、感慨深い気持ちになりました。

後編に続く。