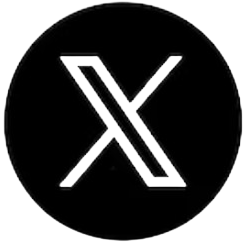2015年に母を見送ったあと、私は9年間にわたり、父の在宅介護を続けました。父は晴眼者ですが認知症を患っていて、日々の生活には細やかな支えが必要でした。けれど、介護を担う私自身がロービジョン(弱視)で見えにくさがあります。
介護をする側が「見えにくい」というのは想像しにくく、「無理なのでは?」「どうやって?」と驚かれるかもしれません。でも、私にとっては見えにくさがあるからこその介護でもありました。
見えにくいから工夫する。音や手の感覚を駆使する。できないことに出会うたびに気づきが生まれました。それは介護のためであると同時に、自分の心を守るための知恵でもあったと思います。今回は、そんな「ロービジョンと介護のあいだで見えてきた工夫や気づき」を、いくつかのエピソードを交えながら書いてみたいと思います。
見えにくい私の工夫あれこれ
手の感覚でお薬管理

父は認知症のほかにリウマチも患っており、たくさんの薬を飲んでいました。その管理は私の役目。
見えにくい私は、触って確認することが自然に身についていて、薬を扱うときも手触りで慎重に判断します。そして念には念をということで、薬局ではすべての薬を種類ごとに袋に分けてもらっていました。飲み方が同じ薬でも、あえて1種類ずつ分けてもらうことで私にとって安心感が増したのです。
それを自分で1回分ずつ小さな袋にセットし、毎回数を確認しながら父に渡していました。
ただ、病状によって薬の種類が増えたり飲み方が変わると次第に区別が難しくなり、薬局に一包化をお願いするようになりました。これが本当に楽でありがたかったのです。確か、それほど料金もかからなかったと思います。見える人にとっても便利ですし、家族の安心にもつながると思います。
定位置を守る作戦

見えにくい私にとって、物の位置を覚えていることは生活の効率に直結します。私が使うものは定位置に置くことが基本。でも、父が物をあちこち動かしてしまうことがよくありました。認知症なので、もちろん「動かさないで」と伝えても難しい。
そこで私は、父が家の中をうろうろとしているときには耳を澄まして行動を探り、あとから変化がないか確認するようになったのです。耳を研ぎ澄ましながら「物が移動しているかもしれない」と心づもりをしておく。毎日繰り返すうちに、そんな習慣が自然と身についていったのです。
逆転の発想や色で工夫
逆ガイドで二人三脚
まだ父が通院できていたころ、私はいつも付き添っていました。父は足腰が丈夫で歩くのが速い。私は白杖を持ってついて行くのに必死です。
そこで、父の腕を持って歩くことにしました。
するとある日、ご近所の方から「娘さんは一人で大丈夫そうだけど、どうしていつもお父さんと一緒なの?」と尋ねられました。「逆なんです。私が父の付き添いで」と答えると相手はびっくり。はたから見ると父が私をガイドしているように見えても、実際は見えにくい私が父を見失わないようにするための工夫だったのです。介護の現場では、外から見ただけではわからない「逆転の工夫」が生まれることもあると実感したできごとでした。

見えにくさの落とし穴
私はクロックポジションでいうと12時から3時の辺りは見えていますが、足元は見えません。なので、床に置いた荷物やゴミ箱など、低い位置にある物に気づきにくいのです。
ある日、ネットスーパーの商品が届き、かごにまとめて冷蔵庫の前まで運んでいたときのこと。そのとき、父の部屋から物音が……。
様子を確認に行くと、父が自分で服を脱ごうとしていたのです。「待ってて!今着替え持ってくるから!」と、急いで着替えを取りに行こうとしたとき……冷蔵庫前に置いた荷物につまずき、ダイナミックに転倒。両ひざとあごを打って、見事な青あざをつくってしまいました。
普段は家具の位置などを覚えているのでつまずかないのですが、介護では予想外のことが次々に起こります。父の行動に気を取られると、自分の安全を忘れてしまう。ロービジョンの私が介護をするということならではの落とし穴でした。
音と色で探る日常
在宅でブラインドライターとして文字起こしの仕事をしている私は、パソコン使用時にイヤホンをしています。ただ、耳をふさぐタイプだと父の気配がわからなくなってしまうため、必ずオープンイヤータイプを選んでいました。耳は私にとって「もうひとつの目」。家の中の小さな物音から父の居場所や行動を感じ取っていたのです。
また「色」も大切でした。濃い色のスリッパを用意して床とのコントラストを強くすることで、父が部屋やトイレにいるかどうかを遠目に確認しやすくしました。
わずかな工夫ですが、これが毎日の安心感につながっていたのです。
それでも起きる、つらい気持ちやイライラをどう減らすか
いらいらを転換する知恵
ある日の朝、あまりにも遅い父の食事にただただ焦りを募らせていました。
認知症では、本人の行動に否定的な言葉をかけてはいけないといわれています。いらいらが募ると、つい「遅い」「早く食べて」などと言ってしまいそうになるのですが、それは絶対に駄目。頭ではわかっていても、心の底からはいらいらがわき上がってきます。どうすればいいんだろう、と悩みました。
そこで私は、気持ちを転換させることにしました。父が食べ終わるのを待ちながら、キッチンの掃除を始めたのです。シンクを磨き、コンロを拭き、換気扇の油汚れを落とす。
父が食事を終えるころにはツルツルの手触りに!同時に私のいらいらも解消されていました。
「相手を否定せず、自分の心を守る工夫」。この経験を通して、私は「人を否定しない」という大切な軸を見つけたような気がします。
ランチョンマットに泣かされた日
あるとき、ランチョンマットが裏返しに置かれていることを父に強く叱られたことがありました。裏表の区別がわかりにくいデザインで、私には判別が難しかったのです。手触りや見た目で確かめたつもりでも、裏になっていると責められる。
こだわりが強くなっていた父にとっては大切なことでも、私にとっては悔しさや悲しさの積み重ね。思わず「見えにくいんだから仕方ないじゃん!」と泣きながら声を荒らげてしまったこともあります。でも、父は私が視覚障害者であることも忘れてしまっていたので「見ればわかるだろう!」とさらに返されるばかり。
そのできごとをきっかけに、私はランチョンマットを裏表のないものに替えました。それは工夫というよりも、余計な衝突を減らし、私自身の心を守るための大切な選択でした。そして、「自分を守るための工夫」もまた、介護の大切な一面なのだと気づいた瞬間でした。

ロービジョンである私にとって、介護の日々は不便との戦いでありながら、工夫の積み重ねによって「できること」を広げていく時間でもありました。
もちろん、転んで怪我をしたり、思いをわかってもらえず涙することもありました。でも、そのたびに「どうすれば避けられるか」「どんな工夫ならお互いに楽になれるか」を考えることで、次の一歩につながっていったのです。
介護は「相手を支えること」だけではなく、「自分の生活を守ること」や「心を守る工夫」を含めた全体の営みだと思います。そして、見えにくさがあるからこそ気づけたこともたくさんありました。
不便をゼロにすることはできませんが、不便をきっかけに工夫や知恵を生み出すことはできます。その工夫が、私にとって介護を続ける力になり、同時に「見えにくくてもできることはたくさんある」と伝えてくれる証しにもなったのです。
執筆:小林直美
アイキャッチ写真撮影:Spotllite
注記のない写真:Unsplash
編集協力:株式会社ペリュトン