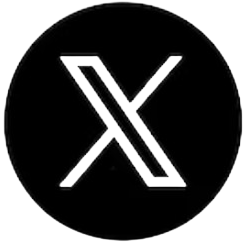「目を閉じて、音だけ聞いてください」
バリアフリー活弁士の檀鼓太郎さんの言葉に、みつきに登録するガイドヘルパー11名が目を閉じました。流れてきた音声は、映画『釜石ラーメン物語』の冒頭シーン。電車の音、鳥の鳴き声、若い女性と年配女性との会話に、耳をすませます。
9月6日と8日の2日間、みつきではガイドヘルパー研修(中級)を開催。500本以上の映画で音声ガイドをつとめてきた檀さんをお招きし、情景が思い浮かぶような情報提供の技術を学びました。
映画の音声ガイドは「UDCast」「HELLO! MOVIE」といったスマートフォンアプリで提供され、視覚障害者の方が映画を楽しめる環境が整いつつあります。
映画の音声ガイドについて、 詳しくは以下のリンクからもお読みいただけます。
講師紹介
檀鼓太郎さん
バリアフリー活弁士・俳優・演出 。劇団“みなと座”を経て、様々な舞台に出演。『兵士の物語』(新星日本交響楽団)、『ピーターと狼』(川越フィルハーモニー)など「音楽劇」の語り・演出。視覚障害者向けに情報提供を行う「バリアフリー活弁士」の第一人者。演劇やプロレスなどのバリアフリー実況の他、結婚式や忘年会でも活動する。

情報を取捨選択し、わかりやすく伝える
今回の研修のゴールは「利用者に届けるべき情報を取捨選択し、わかりやすい言葉で伝える力を高める」こと。参加したガイドヘルパーは、経験半年から13年とさまざまで、「情報提供に苦手意識がある」「初級研修が勉強になったから参加した」など、それぞれの思いを胸に研修に臨みました。
自己紹介を終えた後、さっそく研修がスタート。今関あきよし監督作品、映画『釜石ラーメン物語』を題材にします。まず冒頭シーンを、参加者は目を閉じて、音声ガイドなしで聞きます。
本編の音声だけを聞いた参加者の感想は「地元に帰った女性が、駅で親戚のおばあさんと会った場面かな」「ウグイスの鳴き声がした」「朝の通勤ラッシュを想像した」など、断片的でぼんやりとした印象にとどまりました。

参加者は再び目を閉じ、檀さんの音声ガイド付きで同じ映像に耳をすませます。すると、まるで別世界が広がりました。
「山間の単線レールを、3両編成のディーゼル列車が走る」
「降りてきたのは若い娘、まさみ。モスグリーンのミリタリージャケットを着ている」
「川沿いの、桜が満開の並木道を、おばあさんをおんぶして歩く」
「黄色と青のラインが入ったベンチに座る。ベンチの下には『ペンキ塗りたて』の張り紙」
参加者から驚きの声が上がります。
「情景がバーッと広がった!」
「音声だけではおんぶしていることがわからなかった。『降ろすぞ』というセリフがあったので、いつの間にか車で移動しているのかと思っていた」
「『あと何回見れるかな』というセリフが何を指しているかわからなかった。桜並木のことだとわかって鳥肌が立った」

最後に実際の映像を見て、檀さんがどんな意図で情報を取捨選択していたのかを解説します。
印象に残るのは、おばあさんがペンキ塗りたてのベンチに座ってしまい、ズボンにペンキがついてしまうシーン。映画館では笑いが起きる場面です。
檀さん「視覚障害者の方にとって、『映画館で周りは笑っているけれど、何が起きているかわからない』という状況は珍しくありません。『置いてけぼりで寂しい』という話をよく聞くので、視覚的な笑いのポイントはしっかりと伝わるように意識します」
生まれつき全盲の方にイメージしてもらうポイントは?

後半は参加者が、映画『恋恋豆花』のワンシーンで音声ガイドに初挑戦。ガイドをする前に一度映像を見て、土地や食べ物、建物の名称など、わからない点をクリアにしてから臨みました。
「慌ててコンビニへ戻っていくお母さん」「店先にいる小さな子犬」「商店街、両側にお店がたくさん」
参加者は積極的に言葉を紡ぎます。普段やっているガイドの仕事とは違い、流れるようにシーンが切り替わるため、思うように言葉が出てこず苦戦する様子が伺えました。
檀さんからは、「形容詞が前に出てしまいがちだけど、主語を先に」「具体的な数値を使う」「『慌てている』など声から伝わる情報は言わない」といった、実践的なフィードバックをもらいました。

研修を終えると、参加者から質問が飛び交います。
質問「生まれつき全盲の方に『提灯』と言ってイメージできるでしょうか?」
檀さん「触ったことがないものは、イメージがしづらいでしょうね。そのため、『縦70センチ、横50センチ』といった数字を伝えることもあります。また、見たことは無くても『情熱の赤』『冷静の青』などの色のイメージは持っていたりするので、『赤い〇〇』と色の情報を伝えるのもいいかもしれません」

檀さんは、過去に、ある音声ガイド製作者が「指揮者のように手を握って歌を止める」とガイドをしたところ、映画を観た生まれつき全盲の人から「『手を握る』と聞いて、隣の人と手を繋いだのだと思った」と言われたという話をしてくれました。「今、僕がやるなら、『拳を握るように合図をして歌を止める』と言うかな」と教えてくれました。
質問「語彙力がなく言葉が出てこないのですが、どうしたらいいですか?」
檀さん「ひたすら調べるしかありません。物の名称、建物の名前など、調べたらたいていのものが出てきます。またスポーツのラジオ中継は情報提供の参考になるはずです。テレビを見るか、球場に行って、試合を見ながらラジオの中継を聞いてみるといいかもしれません。どの動きをどう説明しているか勉強になります」
質問「音声ガイドには、ガイドする者の主観が入ってしまいますが良いのでしょうか?」
檀さん「音声ガイドに正解はありません。私は主観が入ってもいいと考えています。主人公が『少女』というイメージなら『ちゃん付け』したり、『頭をパチンと叩く』と擬音を入れたり、『冷めた表情』とあえて伝えたり。そうすることで作品の温度感が伝わると思うのです」

檀さんは「ライブガイドの前には、映画を3回観る」と話します。1回目はストーリーを把握する。2回目はわからない点をピックアップし、説明できるまで徹底的に調べる。3回目に、ガイドのイメージトレーニングをしながら観るそうです。
また上映後は、映画を観た視覚障害者の人たちと感想をシェアするといいます。「あそこはどうなっていたんですか?」と聞かれることもあれば、「そんなことまで伝わっていたんだ」と感じることもあるそう。
参加者の声

研修を終えた参加者からは、前向きな感想が寄せられました。
「利用者さんとの会話が弾みそう」
「音声ガイドの仕事とガイドヘルパーとの業務はつながっていると感じた。視覚情報を言葉で伝えることの可能性が広がった」
「視覚情報を言葉で表現するテクニックを、連続講座でもっと学びたい!」
「映画を音声ガイド付きで観たことがなかったので、利用者さんの体験を知るためにも、観に行きたいです」
今回の研修で学んだ技術は、街歩き、買い物、観光など、さまざまな場面で活用できる貴重なものでした。みつきでは今後も、利用者により豊かな外出を提供できるよう、総合的なガイドスキル向上の機会を提供していきます。
ガイドヘルパー研修「初級編」「上級編」の様子は以下のリンクからお読みいただけます。
執筆・写真撮影:白石果林
編集協力:株式会社ペリュトン