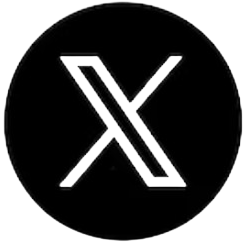旧優生保護法と聞くと、精神障害者や知的障害者への優生手術を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、旧優生保護法において、網膜色素変性症や先天性白内障、アルビノなど、視覚障害も対象疾患とされていました。私は1995年に生まれ、すぐにアルビノと診断されました。旧優生保護法が1948年から1996年まで施行されていた事実を考えると、旧優生保護法は自分と地続きの問題です。
本記事では、今を生きる視覚障害者として、今なお解決していない、旧優生保護法の被害や優生思想の問題を考えていきます。
旧優生保護法は、視覚障害者も対象としていた
旧優生保護法の被害者には、ニュースでよく報じられる知的障害者や精神障害者だけでなく、視覚障害者をはじめとした身体障害者も含みます。旧優生保護法の別表で対象とされた56の疾患のなかには、視覚障害を示す疾患も入っています。(参考:旧優生保護法 外部リンク・衆議院公式サイトより)
視覚障害が主症状となる疾患として、網膜色素変性症、先天性白内障、アルビノ、緑内障、黄斑部変性を伴ういくつかの疾患、色覚異常、先天性の眼球振とうなどが別表に挙げられています。
私は旧優生保護法の施行が終わる前年の1995年に生まれました。旧優生保護法は私と地続きの問題です。
私も、不妊手術の対象とされたかもしれない。そうでなくても、「生まれてこない方がいい」と社会から公然と強く否定されたかもしれない。それは生存を脅かされているに等しいことです。今も消えない優生思想を考慮すれば、旧優生保護法が効力を持っていた時代の苛烈さは私にも想像しきれないほどひどいものでしょう。私にとっては、文字通りの生存の危機です。
社会学者でアルビノの矢吹康夫さんの著書『私がアルビノについて調べ考えて書いた本』(生活書院、2017年)のなかで、結婚する際に任意の優生手術を受けた1938年生まれの男性へのインタビューがあります。アルビノが子どもに遺伝するのを危惧して、配偶者との話し合いを経て、この方自身の同意のもと優生手術を受けています。
この方は夫婦で話し合って手術を受けると決めたと語っていますが、当事者自らが同意して優生手術を受けたことに、当時の社会状況やアルビノが治る見込みのない病気である事実は決して無関係ではないと私は考えています。この方が子どもを作らないと決めた根拠である「潜在意識みたいなもの」がひとりでに作られたとは思えないのです。

科学と政策の両輪で進められた優生学
改めて、旧優生保護法の根底に流れる「優生思想」について考えます。
今では誰もが、かつての優生思想や優生学がよくないものであり、公に肯定してはならないことを知っています。優生思想を肯定する人でさえ、発言する際にはある程度の注意を払う様子が見受けられます。
しかし、優生学の名で優生思想が広まりを見せた20世紀初めには、科学者だけでなく、政治家や宗教家、一般の人々まで、多くの人が優生学の主張を支持しました。この時代、科学は大きく進歩を遂げていき、なかでも、教科書でおなじみのメンデルの遺伝法則やヴァイスマンが唱えた生殖質説は、優生学に大きな影響を与えました。
「生殖に値するよい遺伝子を後世へと伝え、悪い遺伝子は途絶えさせるべきだ」とする思想が生まれ、科学と社会的実践が融合していきました。
優生思想といえば、ナチスドイツが障害者を虐殺した「T4作戦」が知られていますが、優生思想はこうした出来事のみで理解できるものではないのです。
旧優生保護法のもとでの深刻な人権侵害
優生学において特に重視されたのは、知能でした。知能を計測するためにさまざまな知能検査が行われましたが、そのほとんどが文化や価値観の違いを考慮しないものだったため、当時差別を受けていた人々、黒人や先住民族などの非白人、女性などに不利な結果を導き出しました。
また、素行不良な者、つまり社会にとって望ましくない行動を取る人を精神障害者であるとして、優生政策の対象にすることも行われていました。優生学の実践は、何重にも差別的で、恣意的で、およそ科学と呼べるものではありませんでした。それでも、科学者や政治家は、優生学の実践がよりよい未来を導くと信じて、行動し続けていったのです。
日本では戦前・戦中に「産めよ殖やせよ」というスローガンを掲げていたこともあり、優生学は存在しつつも、実践は戦後ほどは徹底していませんでした。しかし、1948年から1996年まで施行された旧優生保護法のもと、多くの強制優生手術が行われました。子どもを望む/望まないに関わらず、人から人生の選択肢を奪う行為は深刻な人権侵害です。

謝罪の言葉や賠償を受け取る前に、亡くなられた被害者も
旧優生保護法には、本人の同意を得ないままに行われる強制不妊手術も数多くありました。優生保護法弁護団の公式サイト(外部リンク)には、全国各地で行われている、旧優生保護法の被害者への損害賠償を求める裁判の状況がまとめられています。
被害者の情報もある程度公開されており、強制優生手術の根拠とされた障害や、裁判の進捗を知ることができます。知的障害者や精神障害者だけではなく、視覚障害者や聴覚障害者の被害者も確認されています。
私も視覚障害者ですが、見えにくさに困って「晴眼者に生まれていたらよかったのに」と思うことはあります。正直に言うと、「こんな身体に生まれたくなかった」と考えた回数は数えきれません。でも、それは私が私に対して思うからこそ、尊重されるべき感情なのであり、誰であっても、善意ゆえであろうと、他人が私にそれを押しつけることは許されません。私に関する決定権は、すべて私にあります。
また、悲しいことに、国から謝罪の言葉や賠償を受け取る前に、亡くなられた被害者もいます。被害者は高齢のため、裁判が長引くほど、不利になるのです。2023年に入って、札幌高裁、仙台地裁、静岡地裁、大阪高裁、熊本地裁で国に損害賠償を命じる判決が出ていますが、どの判決に対しても、国は争う姿勢を見せています。
被害者は人生の選択肢を奪われ、それが人権侵害であるとも知らされず、訴えるに至るまで、多くの時間を要しました。また、障害があることで、司法へのアクセスも難しくなります。そのような状況でありながら、国は相手の不法行為から20年以上経過すると訴える権利を失う除斥期間を主張し、争う姿勢を崩していません。
優生学にもとづいた政策を当然のものとして行い、一般の人々にも優生思想を根付かせておきながら、「被害を訴えるのが遅かったので賠償しません」と主張するのはあまりにも酷です。

おわりに
優生保護法は今や何の効力も持たない過去の法律になりました。しかし、優生保護法によって行われた優生手術の被害への補償は行われておらず、社会に浸透した優生思想もひっそりと、しかし確実に根を張ったままです。
「視覚障害があってかわいそう」と「視覚障害があるなら生まれてこない方がいい」は地続きにある考え方です。それを踏まえると、2023年にあってもなお優生思想への警戒を怠ってはならない状況にあります。私は、生存を脅かされたくはありません。生存のために、優生思想と向き合い続けます。
次回は、今現在の優生思想を見ていきます。
後編はこちら(内部リンク)
<参考文献>
・『私がアルビノについて調べ考えて書いた本』(矢吹康夫著、生活書院、2017年)
・『14歳から考えたい優生学』(フィリッパ・レヴィン著、斉藤隆央訳、すばる舎、2021年)
写真撮影:Spotlite
編集協力:株式会社ペリュトン