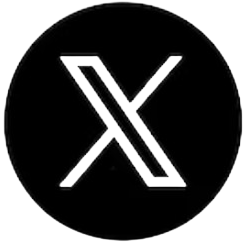マイノリティ性から生じる困難は、独立に生じるのではなく、複雑に絡み合っていることを示す言葉として、「インターセクショナリティ」があります。視覚障害と脚の障害とともに生き、視覚リハビリテーション(以下、視覚リハ)を専門にされてきた吉野由美子さんと、視覚障害、発達障害、セクシュアルマイノリティといったマイノリティ性を併せ持つライターの雁屋優が、「インターセクショナリティ」をテーマに対談しました。
お二人の略歴
吉野由美子(よしの ゆみこ)
視覚障害リハビリテーション協会広報委員、高齢視覚障害者リハビリテーション事例研究分科会代表。1947年生まれ。 先天性白内障によるロービジョンと、原因不明の脚の障害を併せ持つ。東京教育大学附属盲学校(現:筑波大学附属視覚特別支援学校)で高等部まで過ごし、日本福祉大学社会福祉学部を卒業。日本女子大学大学院修了。中途視覚障害者の支援、東京都立大学、高知女子大学での教育に携わってきた。
吉野さんの以前の取材記事はこちら

雁屋優(かりや ゆう)
ライター。1995年生まれ。生後すぐにアルビノと診断される。高校までを普通校で過ごし、茨城大学理学部に進学、卒業。この頃発達障害の一つ、ASDと診断される。自身のセクシュアリティも含め、複数のマイノリティ性を併せ持つ。自身のできることと向き合った結果、文章を書いて生きていくことを決意した。マイノリティの自己決定や医療、科学について執筆している。

「周囲にどんな人がいるか」で障害の自覚は変わる
雁屋 幼い頃は自身の障害をどのように認識していましたか?私は、ずっと普通校で、発達障害の方は大人になってから診断されたのもあって、「自分はアルビノで、目が悪い」と思っていました。
吉野 盲学校にいたのもあってか、ずっと「私は脚が悪い」と思っていたんです。
雁屋さんと私は50歳近くの年齢差がありますね。今は盲学校にも重複障害の子のクラスがあるけど、当時私の通っていた盲学校にはそんなのはなくて、皆は視覚障害者だけど、動ける子ばかりでした。私が盲学校に入学するときには、「肢体不自由の学校のほうがいいんじゃないか」という意見もあったようです。
雁屋 重複障害のクラスができたのは、意外と最近のことだったんですね。周りの環境次第で、障害の認識が変わるのは、私もわかります。私は、眩しさや体調で差はありますが、視力が0.1~0.2程度出ます。これは視覚障害者としては、見える方になるんです。でも、周囲が晴眼者のみの環境で育ったので、私は常に「見えない人」でした。
吉野 私も視力としてはそれくらいなんですけど、フロアバレーボール(視覚障害者向けのスポーツ。ボールを転がして行うバレーボール)なんかをやると、私は動けないけれど、私より見えていない子が軽々と動くんです。だから、自分のことを、視覚障害者というよりも「脚が悪い人」だと思っていたんです。
雁屋 環境の他にも、診断されてから日が浅いものは自覚しにくいこともあります。私は物心ついてからずっとアルビノだと思って生きてきたからもう慣れがあるのですが、診断されてから約5年の発達障害についてはまだ慣れない感じがあります。

どこへ行っても、「違う」ことを突きつけられる
吉野 アルビノというと、視力だけじゃなくて、眩しいのも苦手でしたよね。この部屋は大丈夫ですか?
雁屋 私は平気です。アルビノと一口に言っても、同定されているだけでも原因遺伝子が19種類はあるので、それぞれに眩しさへの耐性や視力、髪や目の色が違います。視覚障害者手帳の等級も、程度の重い2級や3級から、6級の人や手帳がもらえない人までいます。この部屋のブラインドを下ろして、照明を絞って、それでもまだ眩しいと感じる方もいると思います。
吉野 同じ病気のなかでも、かなり違いがあるんですね。私は昔、杖をついていたのですが、肢体不自由で自分で車椅子を動かせる人たちと行動したとき、車椅子の人たちにあっという間に置いていかれたことがあります。車椅子は、案外スピードが出るんですよ。そういう“馴染めなさ”みたいな感覚は経験されたことありますか?
雁屋 どこに行っても馴染めない感覚は私にもありますね。例えば、視覚障害のコミュニティで話をしていたら、視覚障害への差別や偏見が飛んでくることはないけど、ほかのマイノリティ性、発達障害特性やセクシュアリティに関する偏見からくる発言を聞くことは起こりえます。視覚障害に限ったことではなく、どこに行ってもあることなので、当事者コミュニティのようなところに行くのは勇気がいります。
吉野 似たような障害でも、「あなたは私より見えていていいじゃない」と比較されて、私のつらさを「大したことない」と言われた経験もあります。
雁屋 比較して、矮小化されるのはしんどいですよね。私も、他の当事者に「雁屋さんは頭がいいから」と線を引かれたことがあります。いきなり「あなたは違う」と言われて戸惑いました。
吉野 私もそういうことを言われたことがあります。私が高校までいた東京教育大学付属盲学校(現在の筑波大学附属視覚特別支援学校)は、当時全国から視覚障害者のなかでも勉強の得意な人が集まるところでしたし、私は大学に進学しましたが、当時は視覚障害者が大学へ進学することも今よりずっと珍しかったんです。点字で大学入試を受けるために運動して、大学に入学したのが私の世代からでした。
雁屋 そうだったんですね。私がセンター試験(現在の大学入試共通テスト)を受けたときには、点字だけでなく、文字の拡大も用意されていて、拡大も大きさを2種類から選べたので、驚いています。

道を狭めているのは、何なのか
吉野 昔は視覚障害者の進路と言えば、才能があればお琴や三味線、ビアノなどの音楽で生計を立てる道がありましたが、それ以外は、あんま・マッサージ・指圧などの三療に従事する道しかなかったです。盲学校の教員という道もありましたが、かつては三療の指導をすることが、その役割の大部分でした。また、一般社会の方達も視覚障害者=三療という風に思っている方達がほとんどでした。
相談支援の場面で視覚障害を負ったばかりのお子さんに会うと、親御さんが進路の少なさ、就労のことを悲観していることはあります。
雁屋 視覚障害者ではない親御さんが、視覚障害のあるお子さんの可能性を知る機会がないことで、お子さんの進路や就労の選択肢を狭めてしまっているのではないでしょうか。当事者や支援者だけで完結せずに、一般の人にも情報を届けていかないと、先がないと感じます。
吉野 先がないのはその通りなのですが、そう簡単にはいかないと思います。私たちが「あなたは違う」と言われた経験を持つように、障害者のコミュニティでは「私たち同じだよね」と同じになろうとして、少しでも違えば弾き出すようなことが起こっています。
雁屋 たしかに、障害者の世界を作ろうとしてしまっているように感じます。閉鎖的になった先にあるものは、分断であり、それはインクルージョンの概念と逆行するものです。
吉野 社会のなかで自分たちがされてきたことを、障害者の社会でやっていたのでは意味がありません。障害者も、変わる必要があるんです。
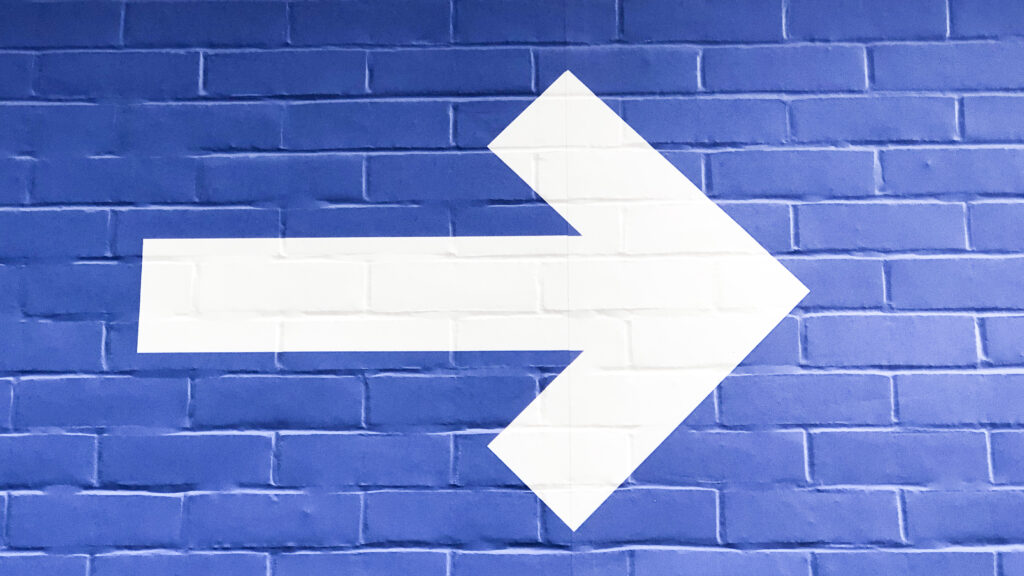
違いを知って、その先へ
雁屋 運動で点字受験を勝ち取った頃からかなり経っていますが、現在でも重度のロービジョンの方が大学進学すると新聞に載るほど珍しく、まだ困難はあるのだと感じます。その一方で、今では大学進学にあたって、どうやって試験を受けるかよりも、入学後どうやって過ごすかが話題の多くを占めています。その意味では変化があるのでしょうか?
吉野 変化しているでしょうね。私は点字で学習していたので、大学の卒論のときは、友人たちが自分自身も卒論があるにも関わらず、私が「たどたどしいひらがな」で書いた卒論を漢字と仮名をまじえて清書してくれました。完全無償のボランティアです。
雁屋 ノートテイカーのようなアルバイトではなく、無償で、ですか。私がその頃に大学生をしていたら、頼める人を見つけられた自信がありません。私が何とかなったのは、何か掲示があれば、メッセンジャーのグループに共有される、もしくは学内システムで内容を見られる環境、そして、レポートはパソコンで書いて提出という、技術に囲まれていた大学生活だったからこそという気がします。
吉野 今でも、自分でコミュニケーションして助けてくれる人を探す必要のある人はいますが、頼まなければならないことも減っているんじゃないでしょうか。理解が進んできているとはいえ、知られているのはわかりやすい障害ばかりです。見えにくい障害や重複障害には、特有の伝わりにくさがあります。
雁屋 発達障害の、「できるけど、やるとすごく疲れる」というのも、なかなか理解されにくいです。視覚障害についても、誤解が多かったり、あまりに雑に理解されていたりして、対応に苦労することもあります。
吉野 私が杖をつくんじゃなくて、車椅子に乗るようになって、電車や道での周囲の態度ががらっと変わったのも、わかりやすく「障害者」になったからでしょう。車椅子に乗っている人にはどうすればいいか、わかりやすいです。
雁屋 わかりやすさには弊害もあるので、何とも言えないところもありますね。例えば、白杖ユーザーの方がスマホを使用していると、「見えているんじゃないか」と怒られた話はあちこちで耳にします。本来、白杖はロービジョンの方も使うものですし、全く見えなくても、音声読み上げなどを使えばスマホを扱えるのに、誤解して偏見をぶつけてくるのはどうかと思います。
吉野 一般の人に障害のことはよく知られていないので、障害のなかにもいろいろあることにまではたどりつけないでいるんだと思います。
雁屋 皆それぞれに困難の形が違っている現実が、社会に浸透した認識になる必要がありますね。「私たちは同じ」ではなく、「私たちは少しずつ違う」。インターセクショナリティ、重複障害を考えれば、なおさら私たちは違っている。そのことを念頭に置いて、やっていくしかありません。

対談を終えて
吉野さんとの対談で、私は知らなかったことにたくさん出会いました。大学入試を点字受験するために運動して権利を勝ち取らなければならなかったこと、特別支援教育における重複障害の児童生徒に対する扱いなど、私はあまりにも多くの歴史を知りませんでした。
私のときと吉野さんのときでは、大学入学のために考えることは大きく異なっています。しかし、「マイノリティだからこそ」コミュニケーション能力がないとつらいこと、障害者のコミュニティのなかでも「違う」と判断されれば、仲間とは扱ってもらえないことなど、共通することも多く、問題の根深さを痛感しました。
健常者と障害者、あるいは障害者同士で小さなパイを奪い合うのではなく、パイが小さい構造こそが問題だと声を上げていく。難しいことですが、惑わされずに構造を見抜き、権利を勝ち取っていくほかないのだと気が引き締まりました。
(記事内写真素材:Unsplash) ※アイキャッチ画像、注釈のあるものを除く
編集協力:株式会社ペリュトン