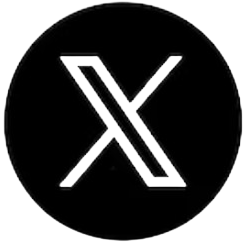パリ2024パラリンピックが開幕します。走り幅跳びの視覚障害クラスで出場する石山大輝選手は、日本代表の旗手も務めます。
競技に打ち込む石山選手の生い立ち、インターハイに出場した経験、大学で一度はやめようと思っていたという陸上の競技歴、そして利用している同行援護のことなどについて、大会前の貴重な時間をいただき、お話を伺いました。
石山大輝選手 プロフィール

順天堂大学大学院在籍。高校1年生の時に網膜色素変性症と診断され、現在の視力は0.3〜0.5程度、中心視野は10度未満。高校時代は三段跳びでインターハイ出場。大学3年生でパラ陸上の走り幅跳びに転向する。パリ2024パラリンピックの日本代表に選出され、日本代表選手団の旗手を務める。同行援護を活用しながら、競技と学業の両立に挑戦中。
バスケのボールが見えづらかった子ども時代
─子ども時代はどのように過ごされていましたか?
石山さん 小学校3年生までは水泳をやっていて、4年生からバスケットボールを始めました。とにかく体を動かすのが大好きでした。昼休みになるやいなや、ボールを持ってグラウンドに駆け込んでいくような少年でしたね。
バスケットボールをしていると、ボールが見えにくかったのを覚えています。でも当時は視力が低い、視野が狭いという自覚がほとんどなく、単純に自分の技術が未熟なんだと思っていました。振り返ると、やはり視野の狭さが影響していたんだろうなと思います。

─「網膜色素変性症」の診断を受けたのは、どのような経緯でしたか?
石山さん 高校1年生のときに、夜盲症の症状が顕著になっていました。日が落ちると視界が極端に悪くなるため、病院を受診し、網膜色素変性症の診断を受けました。診断結果にショックを受けた記憶はありません。子ども時代からなんとなく違和感を抱いてきていたので、ようやく自分の状態について明確な説明が得られて、「やっぱりそうだったのか」という程度の気持ちでした。
だから、診断を受けてから現在に至るまでも、周囲の人々が想像するようなネガティブな感情を持ったことは特にありません。
─陸上はいつから始めましたか?
石山さん 中学1年生から始めて、走り高跳びなどに取り組んでいました。高校に入学すると、顧問の先生から「三段跳びをやってみないか?」と声をかけていただいて、走り高跳びから転向しました。ただ、そのほかにもいろいろな種目に取り組んでいました。
高校3年生のときには、三段跳びでインターハイに出場することができました。実は2年生のときにも、4×400メートルのリレーの補欠メンバーとして会場に行ったことがあります。そのときは走ることができなかったので、個人種目の三段跳びでインターハイに出場できたことは本当に嬉しかったです。
─目が見えないことでの困りごとはありましたか?
石山さん 他の選手たちと比べて、練習時間が制限されることですね。高校では、日が暮れたあとも、ナイター照明のもとで練習を続けられる環境が整っていましたが、僕は夜盲症の影響でどうしても練習時間が短くなってしまいました。周りから遅れをとるんじゃないかという不安は常にありましたね。あとは、よくゴミ箱を蹴飛ばしてしまって怒られていました(笑)。
大学では、陸上を辞めるつもりだった
─それから、大学時代にはどのように陸上に取り組んでいましたか?
石山さん 実は、大学では勉強やアルバイト、就職活動に力を入れたいと考えていて、陸上は辞めるつもりでいたんです。高校時代にインターハイに出られたことで、満足していたところもあったのだと思います。僕は、陸上部のない大学に進学しました。
でも、偶然が重なって、陸上を続けることになりました。大学の入学式のあと、オリエンテーションが終わって帰ろうとしていたときに、友人が近づいてきて「陸上同好会をつくった」と言うのです。
彼は高校時代の同級生で、陸上部のキャプテンを務めていた友人です。偶然、同じ大学に進学していました。まだ部活動にもなっておらず、同好会でしたが、僕はすぐに「入る」と答えました。
最初は5、6人ぐらいのメンバーでした。でも全員がインターハイ出場経験者という、なんとも贅沢な同好会でしたね。練習環境は整っているとは言えませんでしたが、みんなで工夫しながら活動を続けました。大学にグラウンドがなかったので、公営の競技場を利用したり、ウェイトトレーニングを中心に行ったりしていました。
その後、インカレに出場するために正式な部活動にすることを目指しました。大学と交渉して、活動2年目に部活動として認めてもらいました。
あのとき陸上を辞めていたら……と考えると、ゾッとしますね。「陸上部を作ろう」と誘ってくれた友人には心から感謝しています。

パラリンピックでは「自己記録を1センチでも超えたい」
─そうして始めた陸上では、パラ陸上に転向されました。
石山さん パラ陸上に主軸を置きたいと考え、走り幅跳びに転向しました。パラ陸上では、公平に競えるように同程度の障害のある選手同士で「クラス分け」をするのですが、三段跳びには僕が参加できるクラスがなかったためです。
パラ陸上を目指したのは大学3年生のときでした。新型コロナウイルスが流行し始めて、試合数が激減したことがきっかけです。
視力や視野がさほど変わったというわけではなく、とにかく試合に出たかったので、試合数を増やすためにもパラ陸上にも挑戦してみようと考えたのです。
それからパラ陸上を続けていくうちに、「世界で戦っていけるかもしれない」と思うようになっていきました。
─昨年のパリ2023世界パラ陸上競技選手大会では4位、今年の神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会では2位となり、パラリンピックへの出場を勝ち取りました。大会には、どのような思いで臨まれますか?
石山さん 初出場なので、守るものは何もありません。自己ベストを1センチでも超えていけるように、パリで跳んできます。具体的な目標はメダル獲得です。3位以内には絶対に入りたいし、もちろんそれ以上も狙っていければと思っています。
今年の世界選手権では、6本目の跳躍で自己ベストかつ日本記録を出すことができました。走り幅跳びでは、5、6本目で良い記録を出せることが多々あるので、最後の最後まで諦めず、順位をかき回せるようなおもしろい試合をしたいと思います。
そして陸上でのパフォーマンスを通じて、障害者だけでなく、健常者の方々にも勇気や感動を与えられるような存在になりたいです。

同行援護の9割はトレーニングのサポート
─競技を続ける上で、みつきの同行援護を利用していただいています。具体的にどのような場面で活用されていますか?
石山さん 同行援護の90%以上はトレーニングのサポートです。現場への移動はもちろん、ウエイトトレーニングの際には、器具の配置や周囲の状況を教えてもらいます。安全に効果的なトレーニングを行うためには、こうしたサポートが欠かせません。
あとは天候です。晴れと曇りで異なるサングラスを使い分けているので、「今はこのくらい曇っている」とか「もうすぐ晴れそうだ」といった情報をもらいます。これによって、その日のコンディションに合わせた最適なトレーニングができるんです。
─同行援護を利用するメリットは何でしょうか?
石山さん 目の代わりになってもらえることが、本当に助かっています。合宿や遠征の時もついてきてもらい、駅の名前を探すのを手伝ってもらったりします。
以前は友人や後輩に、ボランティアでサポートしてもらっていたんです。無償でお願いすることに申し訳なさがあったので、福祉制度としてきちんと対価が払われるようになったことが嬉しいです。
実は、僕のガイドヘルパーは大学の陸上部の後輩なんです。彼は大学時代からコーチングやトレーニングを専門的に学んでいて、同好会から始まった僕たちの活動において、コーチの役割でした。
彼が同行援護の資格を取得してくれて、今ではトレーニングのサポートだけでなく、並行してフィジカル面のコーチングまでしてくれています。
このように長期的かつ専門的なサポートを受けられる今、同行援護という制度があって本当に良かったと感じます。
─最後に、スポーツに興味を持っている視覚障害者の方々にメッセージをお願いします。
石山さん 視覚障害があると、スポーツを始めるのに不安を感じる方も多いと思います。でも今はパラスポーツの種類も増えていて、さまざまな選択肢があります。例えば、ブラインドサッカーやゴールボールなど、視覚障害者向けに考案されたスポーツもあります。
まずは興味のあるスポーツの見学や応援から始めてみるのもいいかもしれません。応援は僕たちの力にもなります。パラアスリートの姿を見て、何か刺激を感じていただければ嬉しいです。
─石山選手の跳躍を、Spotliteは全力で応援します!本日はありがとうございました。
※同行援護事業所みつきは、Spotliteの運営会社である株式会社mitsukiが運営している福祉サービスです。
アイキャッチ写真提供:日本パラ陸上競技連盟
記事内写真提供:石山大輝さん(※注釈のあるものを除く)
執筆協力:白石果林
編集協力:株式会社ペリュトン