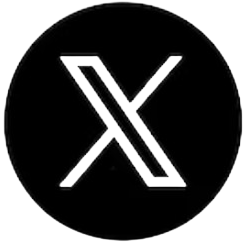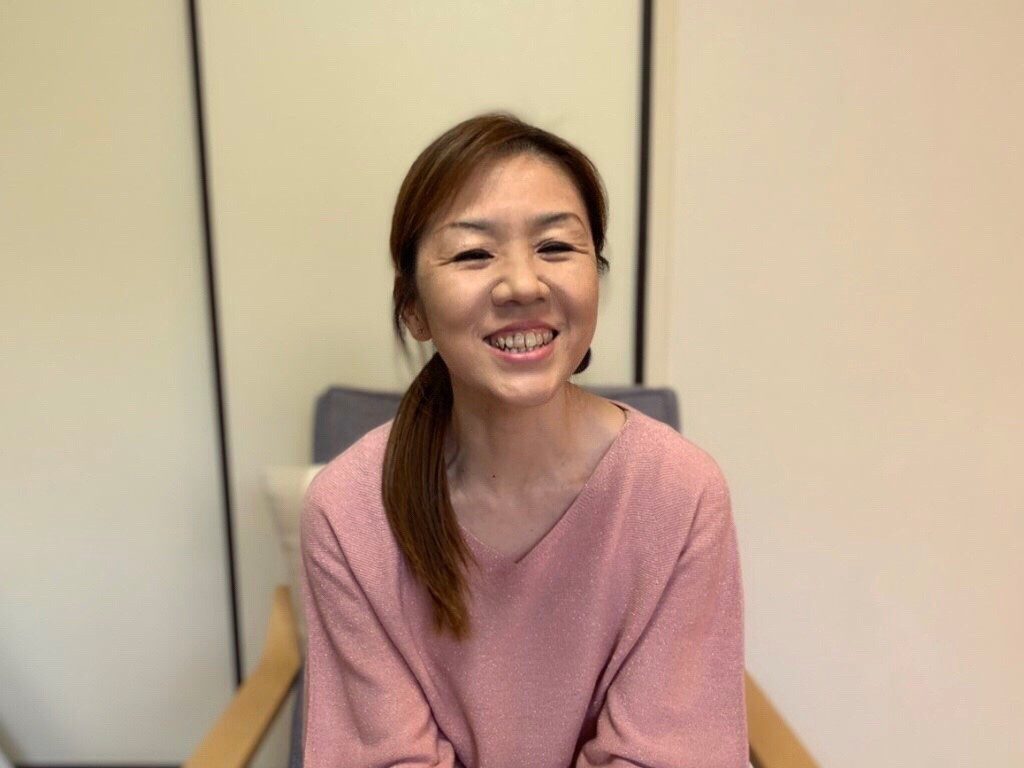「視覚障害があるとキャンプは難しい」
「山や川は好きだけど、テントで泊まるのはなんだか怖い」
そう思っている方は多いかもしれません。でも実は適切な知識や経験、サポートしてくれる仲間がいれば、視覚障害があってもキャンプを楽しめます。むしろ見えていないからこそ感じられる自然の面白さもあるのです。
私は幼少期に視覚を失いましたが、家族や友人とのたくさんのキャンプ体験を通して、自然と向き合う喜びを知りました。本記事では、そんな私の体験をもとに、視覚障害者がキャンプを楽しむためのヒントや工夫、そして自然とふれあう楽しさをお伝えします。
なぜキャンプに挑戦したのか
私が初めてキャンプを経験したのは幼少期、両親に連れられて山の中のキャンプ場を訪れたときです。
バンガローに泊まり、川で遊んだりバーベキューをしたりと、シンプルな1泊2日の体験でしたが、私にとってはとても新鮮で刺激的な時間でした。

家の中では当たり前にできること1つひとつが、自然の中では壮大な冒険のように感じられました。たとえばバーベキュー。家なら包丁で肉や野菜を切ってガスコンロで焼けば完成しますが、自然の中では火を起こすところから始める必要があります。そんな非日常が私にとってはワクワクの連続でした。
視覚障害者にとって、アウトドアはハードルが高いという印象があるかもしれません。でも私は、見えないことでむしろ自然の中で得られる感覚が研ぎ澄まされ、豊かになるのではないかと感じていました。そして「自然の中で生活してみたい」「もっと自然を感じたい」という好奇心がとても強くなりました。
また、両親や身近な人たちのサポートがあったこともキャンプを継続する大きな後押しになりました。幼少期に日常生活の延長として参加できたことで、アウトドアに対する心理的なハードルも下がりました。
森の香り、夜の虫の声、川のせせらぎを全身で感じる

自然の中で寝泊りをするのは、公園散策や日帰りの登山では味わえない特別な体験です。
森の香り、夜の虫の声、川のせせらぎ、そして時折聞こえてくる動物の鳴き声。視覚に頼らなくても、自然を全身で感じることができます。特に夜の静けさと、その中の音の豊かさには驚かされます。暗闇の中で音や気配に意識を集中すると、昼間以上に自然と一体になれるような感覚を覚えます。
晴眼者の友達と、街からかなり離れた山の中でキャンプをした時のことでした。友人が「街の明かりのない夜はこんなに暗いのか」「星の輝きってこんなに明るいのか」と感動していたことがとても印象に残っています。
視覚障害者の立場で彼の感動を想像すると、たとえば「車や電車の音など街の喧噪が全く聞こえない夜の空間」と表現できるかもしれません。人工物の明かりや音がない空間は、怖くて寂しい印象を受ける方も多いでしょう。しかし私は恐怖を全く感じませんでした。むしろ、日頃の人工的な光や音から解放されて自然の中に自分たちが存在することに、心地よさと安心感すら抱いていました。
不便さとどう向き合うか
自然の中で過ごすことには不便や困難もたくさんあります。最大の敵は“虫”です。周囲にいる虫がカブトムシやクワガタばかりなら楽しいのですが、自然の中には害虫もいます。目が見えないと、近くにいる虫に気づかずに刺されたり、触れてしまったりすることもあります。私もこれまでにハチやアブ、ムカデなどの害虫に刺されるなどの経験があります。
虫よけスプレーや長袖、長ズボンなどの対策は欠かせません。それでも完全には防げないのが自然です。
植物も、場合によってはキャンプを楽しむ障害となります。街中と違い自然の中ではあちこちに木があります。街路樹のように規則的に並んでいないので、歩いていると思わぬところで根につまづいたり、顔に枝が当たったりする場合もあります。
トイレも不便のひとつです。キャンプ場ではテントと離れた場所にある共同トイレの建物まで行くことがあります。多くの場合、テントのある広場内は芝生で、舗装された道や目印もないため、1人で移動するのは難しいのです。夜中にトイレに行きたくなったら、同行者を起こして付き添ってもらう必要があります。
このように、見えていないと困難や不便も多いキャンプですが、これらを受け入れられると、日常生活でも心の余裕が生まれる気がします。

視覚障害があってもキャンプを楽しむには
ここまで視覚障害者のキャンプの良い面も不便な面もお伝えしてきました。実際にキャンプに挑戦してみたいという方へ、私なりの工夫や心がけている点をお伝えします。
まずは、キャンプ道具の使い方を予め理解しておくことです。
キャンプでは普段使わないような道具や、普段使っているけれどキャンプ用にアレンジされた形の道具を使う場面があります。買ってみたのはいいけれど、いざキャンプ場で使おうとしたら使い方がわからない……ということもよくあります。私は初めて買ったテントを練習せずに当日立てようとして、構造が把握できず屋根部分を破壊してしまったことや、フレームの設置方法を間違えて変な形のテントが出来上がり、炎天下で何度もやり直しをしたことがあります。
また、火起こしのための道具を使ってみたものの、30分格闘しても火がつかず、最終的にはチャッカマンに頼ったこともあります。
このような苦労をしないためにも、道具は事前に触れて練習しておくことが重要です。
また、初心者からキャンプを始めるのであれば、最初は手軽に始められる方法で少しずつ試してみることも大切です。
キャンプ場にも初心者向けから上級者用までいろいろあります。初心者向けの所では、ほとんどの道具が借りられ、スタッフのサポートが手厚いところも多い印象です。また、近くの宿泊施設のお風呂に入れる場合もあります。
一方、上級者向けになるとキャンプ場は山奥など不便な場所が多くなります。その分、自然は豊かですが、管理人が常駐していない場合も多く、私が知る限りでは道具のレンタルやサポートも基本的にありません。
キャンプを始めるとなると、アニメやテレビ番組の影響からか、あまり混雑しない上級者用のキャンプ場を選ぶ人もいるようですが、まずは日帰りや1泊程度から、初心者向けの整備されたキャンプ場を利用することをおすすめします。
私の友人は、初めてのキャンプで山でのソロキャンプをしましたが、テントを建てたもののキャンプ道具を持っていなかったので水だけ飲んで帰ってきました。
最後に、私が視覚障害者がキャンプする際に最も重要だと考えていることをお伝えします。
それは「主体的に楽しむこと」と「『トラブルさえも楽しんでやろう』の心構え」です。
キャンプをしていると、さまざまなところで自分の思い通りにいかないことが出てきます。自然の中には予期せぬ危険もあるため、思わぬ怪我をしてしまうこともあるでしょう。ここまでに挙げてきたようなトラブルで、同行者や初対面の人に助けてもらうことも、逆に助けることもあるでしょう。特に視覚障害者の場合は、普段は1人でできることも、自然の中では同行者にサポートしてもらわないといけない場面も出てきます。
私は、このような自分ではどうしようもない出来事や、多少のトラブルもキャンプの一部ととらえて楽しむ気持ちこそが重要だと思います。キャンプは同行者との共同作業ですから、積極的に自分のできることや挑戦してみたいことを見つけ、一緒に楽しみながら主体的に参加する姿勢も重要です。できないことやトラブルを恐れて受け身になるのではなく、同行者と一緒にキャンプを楽しんでこそ、本当の意味でのキャンプや自然の中で過ごす良さが実感できると私は信じています。
「自然を楽しもうという気持ち」があれば楽しめるキャンプ

キャンプは「自然を楽しもうという気持ち」があれば誰でも体験できるアクティビティです。見えないからこそ味わえる自然の豊かさや、五感で感じる「本物の自然」は、日常ではなかなか得られない貴重なものです。
不安や不便もありますが、それを乗り越えた先には、驚きや感動、そして自分自身の成長があります。自然の中で一歩踏み出すことで、きっと世界も広がります。もしこの記事を読んで「やってみたい」と思っていただけたなら、ぜひキャンプに挑戦してみてください。
Spotlliteが運営している「同行援護事業所みつき」ではキャンプやアウトドア経験の豊富なガイドさんも在籍しています。もし同行者がいない場合は相談いただくこともできます。みなさんのキャンプが素敵な思い出になることを願っています。
執筆:ケビン
写真素材:Unsplash
ケビンさんが書いてくださった「ブラインドテニス」「釣り」の記事は以下のリンクからお読みいただけます。
Spotliteでは、視覚障害者の外出時にガイドヘルパーを派遣する障害福祉サービス「同行援護」の事業所を運営しております。利用者、ヘルパーともに、若年層中心の活気ある事業所です。余暇活動を中心に、映画鑑賞やショッピング、スポーツ観戦など、幅広いご依頼に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
LINEアカウントはこちら(外部リンク)

※当事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、および香川県に対応しています。
編集協力:株式会社ぺリュトン