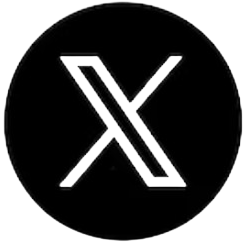視覚障害者が陸上競技をする際、視覚障害者に視覚情報を伝えてサポートする人たちがいます。「ガイドランナー」はトラック競技において、選手とガイドロープを握り合って伴走する重要なサポーターです。しかしガイドランナーは人数が少なく、パラ陸上において課題となっています。
「大会を目指すアスリートはもちろんのこと、趣味でランニングをするだけでも、ガイドランナーがいたら安心感が違います。ガイドランナーがたくさんいれば、視覚障害者がスポーツを始めるきっかけになる」
一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の強化委員長の鈴木徹さんはこう話します。
今回は鈴木徹さんに、視覚障害者競技の現状や課題、鈴木さんが創設を目指す「ガイドランナー認定制度」について伺いました。
一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟(外部リンク)
「選手強化」「若手育成」「社会人教育」を目標に
日本パラ陸上競技連盟(パラ陸連)は、障害者競技会の運営や陸上競技の普及・指導などを行う一般社団法人です。パラ陸連には競技運営や普及、振興などさまざまな委員会があります。
その中のひとつ、強化委員会のトップに2025年4月に就任したのが、鈴木徹さんです。鈴木さんはシドニー2000パラリンピックに初出場。その後6度連続でパラリンピックに出場し、パラリンピアンのレジェンドとして知られています。パラリンピアン出身の強化委員長は、鈴木さんが初めてです。
「自分のプランとしては、2028年のロサンゼルスパラリンピックまで選手やコーチとして参加してから、立候補する予定でした。ただ、コーチや選手として活動する中で、パラスポーツ界のためにやりたいことがたくさん出てきてしまったのです。そんな時に推薦をいただいたので、スピード感を持って実現していくため、早く立候補させてもらいました」
強化委員長の主な役割は、選手強化や合宿の計画、実施などです。また各選手に合わせたサポートやメンタルケアも行います。

「強化委員長としてやりたいことは大きく3つあります。
1つ目はメダル獲得候補となるアスリートの強化です。2つ目は将来のトップ選手となる若手や新人選手の発掘。強化委員会としてはメダルの獲得率を上げることが重要です。
そして3つ目はアスリート教育、特に社会人としての教育です。競技を引退した後、コーチや社会人としてセカンドキャリアをスタートする選手も多いと思います。そのようなとき、社会人としての知識やマナーなどを身につけておくことが重要だと考えています」
鈴木さんは自身が選手やコーチとして活動した経験を元に、これらの目標が選手にとって必要だと感じたといいます。
実体験から見えた「ガイドと選手のマッチング」の重要性
鈴木さんは20歳のとき、2000年のシドニーパラリンピックで初出場を果たします。
「初めてパラリンピックに出場した2000年当時、パラ選手団は予算も少なく、スタッフはほどんどいない状況でした。
日本チームは車椅子と視覚障害の選手がメインで、義足の選手は自分を含めて2人でした。義足の選手は、自分の競技をしながら、視覚障害の選手の移動や食事などをサポートすることになりました。当時は心身ともに疲れていまっていたことを覚えています」
現在はスタッフが増え、選手は自身の競技に集中できる環境ですが、鈴木さんのパラリンピック初出場の時はサポート側の課題が多かったといいます。
鈴木さんはその後、選手兼コーチとして視覚障害の選手のアシスタントをするようになります。
-1024x683.jpg)
「視覚障害の選手をサポートするようになり、ガイドランナーやアシスタントの関わり方が競技に与える影響が非常に大きいとわかりました。距離感の伝え方や性格の相性などによってパフォーマンスと結果に大きな差が出るのです。
視覚障害の場合は、メンタルや技術に加えて、気象状況や明るさなどもパフォーマンスに影響します。ガイドランナーと選手が二人三脚でやって初めて良い記録が出るとわかりました」
「ガイドランナー(ガイド)」とは、ガイドロープを選手と握り合い、声をかけ合ってコースや周囲の状況説明、メンタルサポートなどを行うスタッフです。また「アシスタント(コーラー)」は、跳躍や投てきの種目で、踏み切る位置や方角などを声や手拍子で伝えます。
「視覚障害の陸上選手において、一番重要なのはガイドランナーのマッチングだと思います。選手の身体能力や性格に合わせたガイドランナーがいるだけで、選手のパフォーマンスがさらに伸びる可能性を秘めています。
ただ現在、資格はないですし、そもそもの人数が少ないです。そこで専門的な知識がない人や家族がガイドランナーをやっているケースもあります。そうなると選手がガイドランナーのレベルに合わせることになりますが、本来は逆ですよね。選手がより高いパフォーマンスを出すためには、高い能力を持ったガイドランナーがもっと必要です。シドニーでの経験があったことで、より強く思いました」
この問題を解決するための方法として考えられたのが「視覚障害者ガイドランナー認定制度」の創設でした。
2026年4月開始を目指す「視覚障害者ガイドランナー認定制度」

「視覚障害者ガイドランナー認定制度」とは、鈴木さんが2026年4月からのスタートを目指す、ガイドのための資格認定制度です。
現在、ガイドランナーの資格はなく、ガイドランナーの数も少ない状況です。「視覚障害者ガイドランナー認定制度」では3段階の認定レベルを設け、レベルに応じた研修内容や経験、認定方法を設定しています。
「認定は、ベーシック認定(練習対応)、アドバンス認定(試合対応)、マスター認定(指導・継承)の3段階です。
まずは練習パートナーから始まり、マスター認定では後進を育てたり指導したり、その循環を作りたいと思いました。
認定者の名簿を作れば、各地域で、必要な選手とのマッチングもしやすくなります」
また鈴木さんはこの先、ガイドランナーと同行援護を組み合わせた働き方も実現したいと考えています。同行援護とは、移動が困難な視覚障害者の外出サポートサービスで、移動の援護以外に代読や食事の介助、必要な情報提供などを行います。
「ガイドランナーだけでなく、仕事としてもっと関わりたいと思っている人はいると思います。同行援護従事者の資格が取れたら、選手の生活のサポートや競技場までの送り迎えなどのサポートも可能です。ガイドランナーは収入源が増えますし、同行援護従事者不足の解決につながるかもしれません」
選手とガイドが同じように評価される時代の流れを作りたい
ガイドランナー認定制度に年齢制限はありません。ベーシック認定は「視覚障害者との伴走経験がない方、これから関わってみたい方」、アドバンス認定は「ベーシック修了者や、既に大会で伴走経験のある方」、マスター認定は「国際大会等での伴走経験があり、後進指導に関わりたい方」が対象です。選手経験がなくても、ベーシック認定を取れば練習パートナーとして活動できます。
「陸上選手として活躍していた方はもちろん、趣味として40代や50代から走り始めた方も参加して欲しいです。自分で走るだけでなくて、別の人に還元したいなと思っている方や、平日は会社に勤めて土日に走ってくれる方など、その人に合わせてガイドしてもらえたらと思います。学生の方にも興味を持ってもらえたら嬉しいですね」
鈴木さんは、選手とガイドランナーとの理想の関係性をこう語ります。
「日本では選手に注目が集まりますが、海外ではコーチやメンタルサポーターもしっかり評価を受けています。あくまでも選手が重要ではありますが、僕は選手が頂上でその下にガイドランナーやアシスタントがいるピラミッドではなく、横の関係性だと思うのです。
パラリンピックでは、条件を満たせば選手とガイドランナーがどちらもメダルを授与されます。同等の扱いを受けているのです。国内でも、そのような流れを作っていけたらと思います」
自分なりの表現を見つけてほしい

鈴木さんは幼少期からスポーツが好きで、中学や高校ではハンドボール部に所属し全国大会への出場経験もあります。そして18歳の時に事故により足を切断し、その後走り高跳びを始めました。鈴木さんにとって、スポーツは生きがいだといいます。
「5歳のとき、吃音症を患いました。それが原因となり学校でいじめられることもあり、だから小学校5年生の時には自分から話すのをやめたし、クラスでも発言をしなくなりました。でも、体育の時間はいじめられなかった。僕はスポーツが得意で、いじめっ子よりも上手でした。いじめられないために、スポーツを頑張りました。
スポーツを頑張れば、いじめっ子たちは逆に褒めてくれました。自分の中で、言葉での表現はできないけど、スポーツで表現することはできると感じました。足を失ったときもスポーツが支えてくれました。スポーツが自分の表現方法だったのです。
僕は他の人にも自分が表現する方法を見つけてほしい。スポーツでなくても、歌でも絵でもいいですし、選手ではなくてガイドランナーという可能性もあるかもしれません」
Spotliteでは、今後も視覚障害者のスポーツや「ガイドランナー認定制度」についてご紹介していきます。

執筆:古賀瞳
取材:遠藤光太
アイキャッチ写真撮影:Spotlite
編集協力:株式会社ペリュトン
写真提供:鈴木徹さん(注釈のあるものを除く)