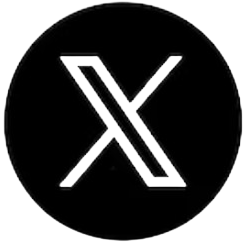こんにちは!ガイドヘルパーのみーちゃんです。
みなさん、“そば”はお好きですか?
同行援護事業所みつきで、2024年12月に、年越しに向けたそば打ち体験のイベントが開催されました。
私は、そのイベントでそば職人としてそば打ちの先生をしたので、そのときの様子をお届けします!
「私は何も持っていない」という弱音がきっかけ

そもそも、なぜそば打ち教室を行うことになったのか、その経緯をお話しします。
猛暑の気配がすぐそこまできていた夏のはじめのころでした。視覚障害者Yさんに、私は弱音を吐いていました。
「私、何も持っていないんです……」
身体を動かすことが好きなYさんは、ブラインドサッカーやブラインドサーフィンなど、本当にさまざまな活動を積極的に行っています。そんなお話を聞いて憧れを抱くのと同時に、Yさんと比較して私は得意なことや武器を何も持っていないなぁと思い、ポロッとこぼした一言でした。
するとYさんは、「どんなことができる?」と優しく聞いてくださいました。本を読むこと、映画を見ること、お散歩が好き、最後に冗談まじりに「そばが打てます」と言った言葉を、Yさんは聞き逃しませんでした。
なぜ打てるのか、何がきっかけだったのか、どんな道具を使うのか、私が驚くほど、それこそ根掘り葉掘り聞かれました。
私のそば打ちの原点は祖父です。
警察官だった祖父は、現役を引退した後に、突然そば屋さんを開きました。もともとは趣味で打っていた“そば”でしたが、祖母の作る“つゆ”との相性が抜群で、子どもの頃から大好きな味です。我が家の年越しそばは、もちろん祖父のそばでした。
祖父がそば屋さんを閉めてから十年以上経ったある日、私はふと祖父のそばが食べたくなり、「祖父に代わり打ってみよう!」と、祖父に弟子入りを志願しました。
そして師匠となった祖父にアドバイスをもらいながら、今年で私のそば打ちも7年目です。
そんな経緯を聞いたYさんは、「そば打ちできるってすごいじゃない!みつきでそば打ち教室しよう!」と私より意気込んでくださいました。
数カ月後、運営の方から「そば打ちの先生をやりませんか?」と打診を受けたときは心底驚きましたが、「本当に叶うなんて!」というワクワク感で、すぐ「やります!」とお伝えし、そば教室開催が決定したのです。
プレそば打ち教室で、課題を洗い出す
開催が決まったのはいいものの、そば打ちを人に教えることは経験がありません。「どんな風に教えていけばいいのかな」と思案していたところ、私の緊張を汲んで、運営の方がプレそば打ち教室をしましょうと言ってくれました。
視覚障害者にとって、どの工程が難しそうか。自宅で確認のための練習とイメージトレーニングをして、プレ教室の日を迎えました。
プレ教室の内容は、視覚障害者の方2名に参加していただき、そば打ち教室の全ての工程を体験してもらった後に、フィードバックをお願いするというものでした。
懸念していた切る工程とゆでる工程は、やはり苦戦し、「難しかった」という感想をでした。加えて、初めてそばを打つ人にとっては、形や固さなどが最終的にどのような状態になるのかがわからないと、進め方が想像しづらいことを指摘していただきました。
このプレ教室のおかげで、さまざまな課題と対応策を考えられました。全体の流れを把握してもらった上で、工程ごとに見本を作っておくこと。本来は使わない湯切り用の器具を使うこと……。難しそうなことも、ほんの少しの工夫で解決できるとわかりました。
少しでもそばを打ちやすい方法を考えながら、自宅での練習をもう一度行い本番に備えました。

「そば職人への道」を開催しました
年の瀬が迫る12月中旬、ついにそば打ち体験教室「そば職人への道」が開催されました。ありがたいことに予定の2倍以上の人数が参加してくれて、老若男女で和気あいあいと始まりました。
当日は、まず参加者に“そばネーム”を決めてもらい、意気込みを話してもらいます。初めてそばを打つ方が多く、皆さんが楽しみにされている様子に私も非常に嬉しくなりました。その後、全体の流れを説明したら、そば打ち教室の始まりです。
そば打ちの工程は、次の通りです。
①混ぜる
灰色っぽいそば粉と、つなぎの役割である真っ白な小麦粉を、さらさらになるまで混ぜ合わせます。

②こねる
塩水を加えながら、こねていきます。
一気に塩水を加えると生地がべちょべちょになってしまうので、丁寧さと繊細さが最も必要な工程です。

③のばす
耳たぶほどの固さにこねた生地を、平べったくしていきます。2~3㎜の薄さにするので、破れないように丁寧に綿棒でのばします。

④切る
大きくのばした生地を蛇腹折りにして、2~3㎜の細さに切ります。

⑤ゆでる
煮立ったお湯でそばを茹でます。そばがお鍋のなかで踊りはじめたら引き上げる合図です。
⑥しめる
お湯からあげたそばをお水でキュッとしめます。今回はめんつゆでいただいたので、私の地元である鹿児島名物さつまあげをはじめ、天かすやねぎなどのトッピングも楽しみました。
ここからは「そば職人兼ヘルパー」の視点で感じたことをお伝えしていきます!
まず、プレ教室の時と同様に、切る工程で苦戦した方が多い印象でした。それでも、手で触って間隔を確かめながら、皆さん本当に一生懸命に切っていました。
こま板という麺の細さを調節できる道具を使うと一定の細さに切れますが、この道具を使った方が切りやすい人、道具がない方が切りやすい人、それぞれでした。
また、参加者の多くから助けを求められた工程が、こねる際に塩水を加える部分です。
塩水の量はそば粉や日によって変わるため、「この分量だけ入れましょう」とお伝えすることができません。完成形の生地を触ってもらい、耳たぶの固さを目指してくださいとお教えして、皆さんに挑戦してもらいました。
塩水は、入れすぎてしまうと二度と取り出すことができません。本当に少量ずつ加えなければならないのですが、生地の固さは急に変化するので、皆さん驚いたのではないかと思います。
この工程が、一番たくさんの「先生!どうしたらいいですか!?」という声が聞こえました。
私も6年目で少しずつ形になってきたそば打ちです。たった1回で超えられてしまっては、そば職人としての威厳が保てません(笑)
調理の難しさというよりも、そばの声を聞きながら工程を進めていくという、「そば職人」としての感覚的な部分も必要なのだと思います。完成したそばを食べた後に参加者からいただいた感想も、「美味しいんだけどね、なんだか……」という納得のいかない声が多かったです。
今回のイベントをきっかけに、皆さんも回数や年数を重ねて、立派なそば職人を目指していただきたいと思います。イベント名が「そば職人への道」ですので、一歩ずつ進んでほしいです!
思いがけずに気づいた、祖父からもらった「そば打ち」という武器

イベント終了後、師匠である祖父に、無事に終えられたことを報告しました。祖父のそばを私が引き継ぎ、皆さんに広まっていくことが嬉しかったようで、祖母と一緒にとても喜んでくれました。私自身にとっても、自分が職人として先生をできるような武器を持っていることに気づかされた、かけがえのない時間になりました。
しかし、そば職人として、ヘルパーとして、反省点もたくさんあります。
「調理」という行為は、分量通り、時間数通りにすれば成功することがほとんどですが、今回のように微妙な調節や、感覚的な部分での熟練が必要な工程も出てきます。基本の「キ」である情報の言語化が最も必要な部分で、あまり上手く言語化できず申し訳なかったなあと反省しています。
一方で、情報伝達ができた部分や便利な道具を使った工程では、安全が守れたり戸惑うことなく調理したりできることもわかりました。
次回開催時には、皆さんが少しでもそば職人に近づけるよう、どんどん改善していきますので、ぜひご参加くださいね!
執筆:みーちゃん
記事内写真撮影:Spotlite(※注釈のあるものを除く)
編集協力:株式会社ペリュトン