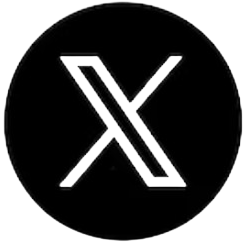近年、目覚ましく進歩している生成AIツール。
読み上げ機能や画像認識機能などの発達により、視覚障害者の生活を支える技術としても注目されています。
本記事では、視覚障害者がスマートフォンなどの身近なデバイスを活用して、最新の生成AI技術を日常生活でどのように使うのか、具体例や利用者の声をまじえて解説します。
生成AI活用に関心のある視覚障害者やご家族の方は、ぜひ読んでみてください。
SpotliteのYouTubeチャンネルで、動画でも紹介しています。
生成AIの概要と視覚障害者へのメリット
生成AIは、言語処理や画像解析などの技術を活用し、さまざまなことをサポートしてくれます。例えば、話し言葉のような漠然とした質問から情報収集をしてくれたり、テキストの自動生成などの機能で文章を作成してくれたりします。この数年耳にすることが多くなった“ChatGPT”はその代表例です。誰でも手軽に無料でも利用可能で、質問に対する回答や文章作成をサポートしてくれます。

視覚障害者が生成AIを活用することで、以下のようなメリットがあります。
- 情報収集の効率化
画像読み取り機能や音声読み上げ機能を活用することで、文章や画像などの視覚情報を聴覚から得ることができます - 自立したコミュニケーション
音声入力から文章作成をサポートしてもらうなど、支援者がいない場合でもコミュニケーションのサポートとして活用できます。
実際に、Spotliteが実施したアンケートからも、当事者の方がさまざまなAIツールを日常生活で活用していることがわかりました。
音声読み上げだと同音異義語の誤字に気付きにくいので、生成AIで漢字の文字校正をしてもらうことがあります。
視覚障害者向け具体的なAIツールの紹介と使用例

ここからは、よく使われる視覚障害者向けの生成AIツールを紹介します。
Seeing AI(Microsoft)
Microsoftが提供するSeeing AIは、iOS向けの無料アプリです。スマートフォンのカメラを使い、周囲のシーン、テキスト、人物を認識して音声で詳細に説明してくれるため、視覚障害者が外出先や自宅で簡単に情報を得られるツールとして評価が高いAIアプリです。
ChatGPTのリアルタイムビデオ共有機能
最新のChatGPTアプリには、カメラ映像をリアルタイムで共有し、その内容を生成AIが音声で解説する機能が搭載されています。この機能によって、パソコンの画面や外出先の映像を即座に把握することができます。(この機能は、有料のPlus契約が必要な場合もありますので、詳細は公式の最新情報をご確認ください)
Be My Eyes(Be My AI機能)
Be My Eyesは、視覚障害者とボランティアを繋ぐサービスとして広く利用されています。さらに、最近ではAIを活用した「Be My AI」機能が追加され、ユーザーが撮影した画像の内容を自動解析してリアルタイムで説明してくれるので、ボランティアとすぐにつながらない場合でもサポートが可能です。
Google Lookout
Google Lookoutは、Android向けのアプリで、スマートフォンのカメラを通じて周囲の情報を解析し、視覚に頼らず音声で状況を伝えるツールです。視覚障害や低視力のユーザー向けに設計されており、日常の物体認識や情報取得を強力にサポートします。
アンケート結果から見る人気ツール『Seeing AI』の使い方と活用方法

弊社が実施したアンケートからは、Seeing AIを活用している当事者が多いことがうかがえました。
具体的な使い方は、以下のような事例があります。
- 基本的な使い方
iPhone、iPadなどのiOSデバイスにSeeing AIをインストールします。アプリを起動してカメラを向けるだけで、周囲の状況やテキスト、人物を瞬時に認識し、音声で情報提供をしてくれます。 - 日常生活での活用例
- 移動時の情報取得
駅やバス停の案内表示、道路標識などを読み取り、1人での外出をサポート。 - 買い物や外食時の利用
商品ラベルやメニューを読み取り、内容を知ることができるので、1人で気軽に買い物や食事を楽しめる。 - 家庭内での活用
テキスト読み上げ機能を利用し、書類や郵便物の内容確認が可能。家事や日常生活の視覚情報の補完として活用できる。
- 移動時の情報取得
- 今後の期待とアップデート
定期的なアプリのアップデートにより、機能が強化され、より多くの利用シーンに対応できるようになっています。この点が、利用者から高い評価を受けています。
Seeing AIは、視覚障害者がより自立した生活を送るための必須ツールとして、今後も多くの場面で活用できるようになるのではないでしょうか。
最後に
本記事でご紹介した各種生成AIツールは、視覚障害者が日常生活の質を向上させる大きなサポートとなるでしょう。最新技術を積極的に取り入れることで、情報へのアクセスが容易になり、より便利になることで、生活がより充実することが期待できます。ぜひ、これらのツールも活用してみてください。
記事内写真撮影:Spotlite(※注釈のあるものを除く)