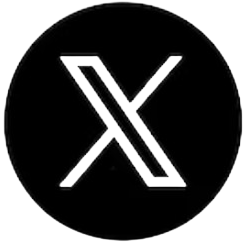私は、都内の私立大学で英語を学んでいる大学2年生です。趣味は読書と写真を撮ることで、普段は東京で一人暮らしをしています。見え方は全盲です。
今回は、私が現在挑戦中のカナダ・アルバータ州での留学についてお伝えします。
留学は「憧れ」から「絶対条件」へ。私の大学選び
英語に夢中になったのは中学生の頃。洋楽の歌詞を知りたくて辞書を引いたり、海外の映画を音声ガイド付きで何度も観たりしているうちに、「英語を使って世界中の人と話してみたい」という夢が芽生えました。
高校生になり進路を考え始めた時、その夢は「大学在学中に必ず英語圏で長期留学を経験したい」という明確な目標に変わりました。
しかし、そこには大きな壁がありました。それは、私の視覚障害です。
近年、留学プログラムが充実している大学は増えていますが、視覚に障害のある先輩方からは「サポート体制が不十分で留学を諦めた」といった現実的な声も聞こえてきました。それは私にとっても不安材料でした。
それでも、私はどうしても留学を諦めたくありませんでした。そこで、「留学が卒業に必要なカリキュラムとして組み込まれている大学」を探すことにしました。留学が前提になっていれば、視覚障害のある私にも、留学しやすいのではないかと考えたのです。
こうして進学したのが、今の大学です。私の学科では、2年次にカナダ・レスブリッジへの半年間の留学が必修になっており、ホームステイをしながら現地大学で学ぶプログラムが用意されています。

留学準備は「率直な対話」と「信頼関係」から
入学当初から「私は絶対にカナダに行く」という思いを胸に、英語の授業やTOEICの勉強に励んできました。
2年生になると、大学の先生、留学サポートのエージェント、そして現地大学のスタッフと、何度も面談を重ねました。その中で私が一番大切にしたのは、「自分にできること」と「サポートが必要なこと」を、正直に、具体的に伝えることでした。
たとえば、東京で一人暮らしをしていたこと、大学構内も基本的に一人で移動できていること、パソコン操作が問題なくできること……などです。
これらは、私の自信にもつながる「強み」です。全盲だからといって「何もできない」わけではない。そのことを知ってもらい、先生方やスタッフの不安を少しでも和らげたいと思いました。
一方で、資料のデジタル化や移動時のサポートなど、どうしても必要な配慮については素直にお願いしました。こうした率直な対話の積み重ねが、信頼関係を築くうえでとても重要だったと感じています。「どうすれば安心して学べるか」を一緒に考えてくれる環境が整っていきました。

「特別扱い」ではない対応が嬉しい。サイクリング体験も!
カナダへ渡ったのは8月上旬。寒さで知られるアルバータ州ですが、到着した頃は夏の暖かさが残っていました。
私をホームステイで迎えてくれたのは、メキシコ出身の快活なご夫婦。視覚障害について事前に理解した上で、快く受け入れてくださいました。
生活の基本は「自分のことは自分で」。自室の管理は私が行い、キッチンやリビングなどの共有スペースでは、「物の位置を変えない」「床に物を置かない」といったルールを作ってくださり、安心して生活できるように配慮してくれています。
嬉しかったのは、「障害があるから特別扱い」ではなく、「他の生徒と同じようにさまざまな体験をしてほしい」という姿勢です。ホストファミリーの友人たちとの食事、キャンプへのお出かけなど、たくさんの出会いや発見があります。
ある日、ホストファーザーが「サイクリングが好きなんだけど、やってみたい?」と聞いてくれました。私が「やってみたい!」と答えると、なんと2人乗り専用のタンデム自転車を知人から譲ってもらい、一緒に走ることができました。風を感じながら走るその体験は、楽しくて新鮮で、今でも心に残っています。

「違い」や「戸惑い」も、すべてが学び
もちろん、楽しいことばかりではありません。まず感じたのは、移動の難しさです。
日本のような点字ブロックや音響信号機はほとんどなく、歩道も広すぎて、頼れる目印が少ないのです。建物と建物の間隔も広いため、壁を伝って歩くといった方法も使えません。正直、単独での移動は今の私にはかなり難しいことです。
そこで今は、ホストファミリーや友人の助けを借りて少しずつ道を覚えたり、単独での移動が難しい方々向けのライドシェアサービスを使って通学したりと、自分に合った方法を模索しています。
また、もうひとつの大きな壁が、コミュニケーションスタイルの違いです。
カナダでは、日本以上にアイコンタクトが重視されます。相手の目を見ることが、信頼や関心を示すサインとされています。しかし、私はそれができません。
視線を合わせられないことで、先生に質問したくても、今話しかけていいのかがわかりません。ディスカッションではテンポが速く、「今だ」と思っても、すでに話が進んでいたりします。
「ちゃんと聞いているつもりだけど、視線が合わないことで誤解されていないかな……」そんな不安がよぎることもあります。でもこれも異文化の一部。この中でどうやって自分らしい居場所を作るか、日々考えています。
カナダで見つけた、ふたつの目標

カナダに来て約1ヶ月。楽しいこと、嬉しいこと、悔しいこと、難しいこと。すべての経験が、私にとってかけがえのない学びになっています。
今の目標は、2つあります。
ひとつめは、この土地での「自立」を模索すること。
東京での一人暮らしでは、「ほとんどのことは自分でできる」と自信を持っていました。でも、カナダでは状況がまったく違います。大切なのは、「人の助けを借りながら、どこまでなら自分でできるのか」「どこに挑戦できる余地があるのか」を見つけていくこと。柔軟な自立を目指して、地に足をつけて生活していきたいと思っています。
ふたつめは、自分をもっと知ってもらうこと。
白杖はカナダでも比較的知られていて、バスの運転手さんや道ですれ違う人が声をかけてくれることもあります。でも、この町で日常的に白杖を使って歩いている人にはまだ出会っていません。
だからこそ、「視覚に障害のある人がどんなサポートを必要としているのか」「どんなことは自分でできるのか」を、もっと伝えていく必要があると感じています。
「私はアイコンタクトができないけれど、あなたの話を真剣に聞いています」「一人で移動したいけれど、時には助けてほしいです」。そんな気持ちを、第二言語である英語で、どう伝えるか。これもまた、この留学でしかできない大きな挑戦だと思っています。
留学は、キラキラしたことばかりではありません。ですが、困難にぶつかるたびに、「一人じゃない」と実感します。手を差し伸べてくれるホストファミリーや友人、親身に支えてくれる大学の先生方、そして日本から応援してくれる家族。多くの人に支えられながら、私はこの場所で少しずつ、自分らしい道を歩んでいます。
視覚に障害があっても、世界は広がる。カナダの青い空の下で、そんな実感を日々かみしめながら暮らしています。

執筆:かなう
記事内写真提供:かなう
かなうさんが一人暮らしを始めたときの様子は以下の記事からお読みいただけます。
編集協力:株式会社ペリュトン