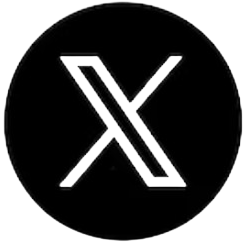横浜市立みなと赤十字病院に眼科部長として勤務する椎野めぐみさん。
昨年より視覚障害者に対するロービジョンケアを本格的に始め、院内での交流会や音楽会、パラアスリートの講演会など様々なイベントを企画しています。
椎野先生の取り組みを前編、後編の2回に分けてご紹介していきます。
後編では、専門的に勉強されたケアの手法や眼科医としての役割、これから取り組みたいことをお伝えします。
前編のインタビュー記事はこちら
略歴
神奈川県生まれ。浜松医科大学医学部卒業後、横浜市立大学付属病院等を経て、現在はみなと赤十字病院眼科部長。毎月1回、横浜市立大学ロービジョンケア外来も担当。
2018年上智大学グリーフケア研究所臨床傾聴士を取得。趣味は、美味しいものを食べること、感動する本を読むこと。
インタビュー
視覚障害とグリーフケア
ー視覚障害者と関わる中で大切にしていることはありますか?
同じ土俵に立って話を聞くことです。「医者としてではなくて、お話を聞きますよ。あなたのお困りごとや辛い気持ちを教えてください」と伝えることが、当事者にとって一番負担がないのかなと思います。診察の時は、「ここは見えますか?あれはどうですか?」と、どうしても客観的な事実だけを聞いていきます。それでは患者さんの心の悩みまでは解決できない。
心理学でナラティブという手法があります。自分のこれまでの人生を聞き手に語ることで、自分自身のことを物語として捉え、人生をもう一回生き直すことができるのです。視覚障害の患者さんに対して、同じ立場でその人の話を真剣に聴くということを意識しています。
ー心理学などの専門的な勉強をされているんですね。
はい。グリーフケアを勉強しています。親族や家族など親しい人と死別など、色々な悲嘆(グリーフ)を体験して悲嘆の日々を過ごしている人に寄り添いながら立ち直るきっかけを探すという分野です。
実は、私の妹が2011年に44歳で癌で亡くなりました。その時、医療者であるのだけれども、私は何も出来なかったんですね。
人の死というのは、一人称の死、二人称の死、三人称の死に分かれるのです。三人称の死は一時的に悲しくても忘れられるのですが、二人称の死、つまり身近な誰かの死は忘れられないのです。私の場合、家族であり、かつ医療者でもあるという立場が非常に辛くて、病気のことがよく分かるけれど治してあげられないというジレンマがありました。妹にはまだ高校1年生と小学5年生の子どもがいましたし、私の母も娘を亡くして嘆き悲しみ精神的に参ってしまいました。「残された子どもたちや私の母の悲嘆に対して何ができるだろう」と思った時に、たまたまグリーフケアの講演会を知って参加したのです。それから、グリーフケアを専門に勉強する上智大学グリーケア研究所の社会人コースに2年間通いました。グリーフとは、それまで持っていたものを失う、喪失する時に出てくる、悲嘆という意味なのです。
ーそれが視覚障害者のケアにも活かされているんですね。
グリーフケアを学ぶことで、同じことが視覚障害者にも当てはまるのではないかと思いました。視覚というそれまで持っていた機能を失う時、悲嘆(グリーフ)が生じます。視覚を失う時に、患者さんは今の状態を治してもらえると思って病院に来ます。「治せない」と言われる時の衝撃は計り知れないと思うのです。死の宣告と同じくらい重いことです。軽々しく口にできないと気付きました。視覚を失いつつある方の心にまで寄り添う必要があると考えています。

眼科医として何ができるのか
ー視覚障害者の話を聞く中で印象に残っている出来事はありますか?
私が初めて視覚障害者の方とじっくりお話した時のことです。最初に「先生に聞きたいことがあるんです。眼科医は見えなくなってから何もしてくれないじゃないですか。そこを眼科医としてどう思ってるんですか?」と問われました。嫌味などではなくて単純な疑問だったのだと思います。だからこそ、グサっとくる言葉で、返す言葉がすぐには見つかりませんでした。
ー今、その言葉について改めて思うことはありますか?
医者というのは病気が治せなかったときに敗北感や無力感があるのです。学生時代からずっとエリートで、医者になっても患者から感謝されるのが当たり前、だからいざ治せない患者がいた時に、そういう感情に対処するのが苦手なのかなと思います。
加えて、医者と患者の関係は教師と生徒みたいなもので、上下の関係になりがちです。患者の方が弱い立場であって、先生の言うことを聞かなきゃいけない。そのため、治療ができなくなった時患者さんに対して適切な対応ができないのではないかなと思います。
ーそういう中で眼科医がやるべきことはどのようなことでしょうか?
病気しか見ないのではなく、その人の人生にまで目を向けることだと思います。視覚障害になると、その人の生きざまが全部がらっと変わるわけです。もちろん、医者もその人の人生全てに関わることはできません。まずは視覚を失ったということに対して医療的な処置を行ったうえで、心のケアが必要だと思います。
例えば、患者さんの気持ちが混乱している時期があります。その時間は必要な時なのですが、医者として立ち直るきっかけを提供することはできます。どこにもつながれず、一人で引きこもっていたら長引いてしまいます。福祉施設や行政機関などの社会資源に関する情報を伝えるのもそうですが、病院の診察室以外の場所で「あそこに行けば何か話を聞いてくれる」「自分と同じような人がいる」という場を作るのは大きな意味があると思います。
ーロービジョンケアを進める上での課題は何でしょうか?
眼科医の中で情報の共有がまだまだ少ないことです。それぞれの先生が病気を治そうと一生懸命治療されているのですが、もし治らなければ、ロービジョンの専門病院へすぐ結びつけることが大切だと思います。手術するときに他の病院を紹介するのと同じです。全ての眼科医がロービジョンケアのエキスパートになる必要はありません。専門分野の一つとして眼科の中で認知度を上げていく必要があると思います。
ただ、患者さんもいきなりロービジョンケアをする病院に行ってくださいと言われても「何もしてくれないところになぜ行かなければいけないんだ、もう見放されたのか」と抵抗される方もいるので、ロービジョンケアのことを正しく伝えることは大切です。
ー眼科医以外とも連携する上で必要なことはありますか?
地域性だと思います。近くに視覚障害者のための福祉施設や教育機関でどんな施設があるかということは、私もロービジョンに関わる前までは詳しく知りませんでした。県内の盲学校やライトセンターに見学に行ったのも、2年くらい前が初めてです。「この困りごとはここに相談すればいい」ということが地域の中で広く認知される必要があると思います。
医療者として、cure(キュア:治療)は当然行うのですが、care(ケア:支援)になるとちょっとスタンスが違ってくると思います。cure(治療)は病院だけでできても、care(ケア)は多職種で対応しないとできません。医師もその一員であり、チーム医療をロービジョンの中でも行っていきたいと考えています。

知るために、当事者の話を聞く
ーこれから椎野先生が新しく取り組みたいことはありますか?
毎月1回行っている集まりは、私やヨガのインストラクターの先生が中心になって進めているのですが、今後は参加されている患者さんが中心になって、新しい患者さんと話ができるようになればいいなと思っています。その中で私も同じ仲間としてやっていく。そうなると、もう医療ではなくなってくるかもしれないんですが。
この前、病院の空きスペースにカフェを作りたいなという構想立てたことがありました。毎日じゃなくてもいいのですが、カフェがオープンしている時は、ざっくばらんに色々な話ができる場所を作りたいのです。近隣にも似たようなことを考えていたり、既に実践されている先生がいらっしゃるので、お互い勉強しながらつながっていければいいなと思っています。
ー社会の中で足りていない視点は何でしょうか?
今、障害者を受け入れるというときに生産性ばかり言われているじゃないですか。その中で視覚障害者本人が感じる引け目はものすごく強いと思うのです。一人で日常生活の維持ができなくなって「自分が見えなくなっていくこと=人の世話にならなければいけない」と考える時、自立性が損なわれたと感じるでしょう。
現代の社会は元気で健康であることが第一の目的になっていますが、誰でも老いていく過程で障害は出てきます。今できていることが、歳を取りいつかできなくなるのであれば、その時にどうやって住みよい社会を作るかというのは、視覚障害に限らず人間社会共通の課題なのだと思っています。
ーそのために大切なことは何でしょうか?
やっぱり知ることだろうと思います。そして、知るためには当事者の話を聞くのが一番です。最初はどうしても他人事なのですが、当事者の話を聞くとその人の悩みや辛さや感じることができて、自分の事として考えられるようになるのです。そうなった時、初めて患者さんに寄り添った関わりができるのかなと思っています。
椎野めぐみさんのインタビュー終わり