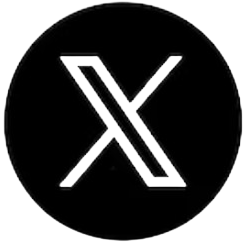同行援護事業所みつきでは、8月22日と23日の2日間、ガイドヘルパー研修(上級)を開催しました。今回は特別講師として、元テレビ局アナウンサーで話し方講師の野村朱美さんをお招きし、「ワンランク上のコミュニケーション」をテーマに研修を実施。気持ちのいい挨拶、相手に安心感を与える話し方、さまざまな利用者さんへの対応などを学び、総合的なガイドスキルの向上を目指します。
参加者は経験豊富なヘルパーの皆さんで、ガイドヘルパー歴1年未満の方から16年のベテランの方まで、それぞれ異なる背景を持つメンバーが集まりました。
講師紹介
野村朱美さん

テレビ山梨・テレビ神奈川の元アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活動されています。「うたうからだ学®︎」認定講師の資格も取得され、声の仕組みを科学的に分析した指導を行っています。声の専門家、話し方講師に加え、ガイドヘルパーとしても活躍されています。
※7月に実施した「初級編」の研修の様子は以下のリンクからお読みいただけます。
口の周りにソースがついていたら、どう伝える?
研修は、野村さんの講義からスタートしました。
あいさつの基本や傾聴のテクニックなど、ガイドヘルパーとしてはもちろん、日常生活でも役に立つコミュニケーションのテクニックを学ぶことができました。
講義を受けて、参加者同士で自己紹介や質疑応答のロールプレイを実施し、朗らかな雰囲気で研修が進みます。

野村さんによる講義のあと、実際にあった事例をもとにガイドの場面でのロールプレイが行われました。
1. 身だしなみを伝える
口の周りにソースがついている、洋服にシミがあるといった、伝えづらい場面での声のかけ方法を検討しました。参加者からは「ストレートに伝える」といった意見のほか、「お弁当ついてますよ」と独特な言い回しで声をかけたという経験談が共有されました。「若いのに、“お弁当”って言うんだね」と利用者さんが反応し、会話が盛り上がったそうです。
鼻毛が出ていることに気づいた時の対応では、あるヘルパーからは「鼻毛が出ていることに外で気づいた。その場ではどうすることもできないので、家に到着した時にコソッと伝えた」という経験が共有されました。
野村さんからは、言いにくいことを伝える際の「枕言葉」の重要性が説明され、「視覚障害者の目の代わりとしてお仕事していますので、お伝えさせていただきますね」「お気を悪くされたらごめんなさい」といった前置きの使い方が紹介されました。

2. 混雑したコンサート会場でのグッズ購入
100人以上が並ぶグッズ売り場で、優先案内された利用者がゆっくり選んでいる状況での対応を議論しました。
「混んでいるので急ぎましょう」といった直接的な表現ではなく、「このアーティストは人気がすごいですね」「もうすぐライブが始まるので早めに会場に向かいましょうか」「トイレが混んでいるので先に行っておいた方が良さそうです」などと、やんわりと状況を伝えるという参加者もいました。
野村さんは「伝える」ために重要な3つのポイントについて、「タイミング」「話す内容」「相手との関係性」と紹介。「なかでも一番大切なのは相手との関係性」だとし、「言いにくいことも伝えるのがペルパーの仕事。そのためまずは、関係性を構築することが大切です」と呼びかけました。
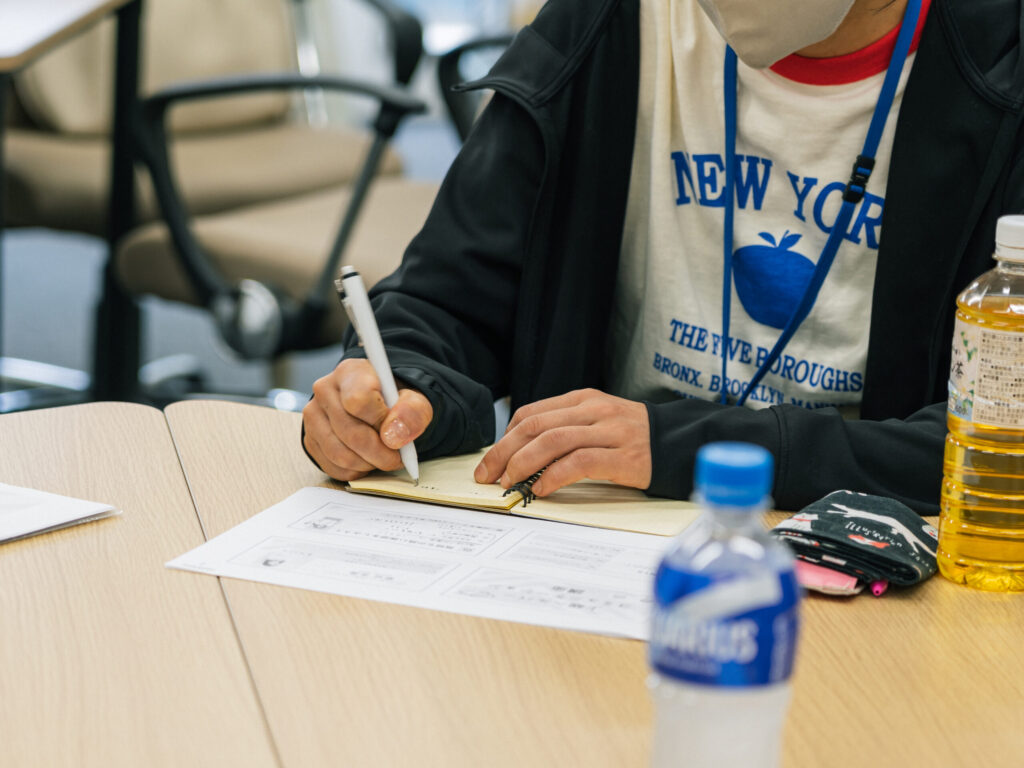
3. セクハラ的な場面への対応
カラオケボックスで距離が近すぎたり、不適切な発言をされたりした場面での対処法を検討しました。利用者に悪気はない可能性もあり、すぐに「セクハラ」と判断するのはなかなか難しいという声もありました。そのため、たとえば隣にピッタリと座られた場合は、「感染症が流行っているので」「飲み物をとってきます」「この部屋は広いのでもう少し離れても大丈夫ですよ」と伝え、まずは距離を置いて様子を見るといった意見が交わされました。
「彼氏・彼女いるの?」といった会話を悪気なくしてしまう人も少なくないという意見には、運営チームから「ちょっと違和感を感じたら、そういう会話を気やすくしにくいムードを」と話がありました。
そのほか不適切な発言をされた場合は、深刻にならないトーンで「何言ってるんですか?」と返す、その場は適当に返答して事業所に報告する、「やめてください」とストレートに伝える、といった意見も。野村さんは「これらの対応について正解はない」とし、臨機応変に対応するための引き出しをたくさん用意しておくことが大切だと呼びかけました。
講義を終えると、参加者は次のような感想を述べました。
「普段やっていることを、コミュニケーション技術として分析できて勉強になった」
「一人暮らしの高齢の利用者さんは、喋りたい人も多い。傾聴を意識していたものの、自分の気持ちを言語化するという点をさらに意識したいと感じました」
「情報の蓄積も大事。些細なことでも事業所へ報告してほしい」

次に、ガイドをしている時に実際に起きた困り事や成功体験などを共有しました。
心理的につらい状態の利用者について
仕事や人間関係の悩みから被害妄想的になってしまっていた利用者への対応では、「いいところを見つけることを心がけた」という経験が共有されました。「治療も、普段の生活も頑張っていた。応援してあげたいという気持ちを忘れずに接していた」といい、最後まで信頼関係を維持できたという体験が語られました。
電車の駆け込み乗車について
あるヘルパーは、利用者から「今の電車に乗りたかった!」と指摘を受けた経験を話しました。駆け込み乗車を避け、安全を優先したヘルパーの判断について、参加者からは「間違っていない!」と声が上がり、運営チームからも「事業所としても走らないことが望ましいと考えています。周知したいです」との見解が出されました。交差点で走って利用者が転倒した事例の共有もあり、安全第一でガイドすることの重要性を確認しました。
情報共有について
参加者からは、「事業所に対し、どこまで報告すればいいのか迷ってしまう」という悩みも上がりました。
「道ゆく人に白状を蹴飛ばされた。折れたわけではないけど、報告すべきなのか……」「トラブルになったわけではないけれど、タクシーの運転手さんの様子が少しおかしくて……」こういった話に対し、運営チームは「情報の蓄積が他のヘルパーや利用者さんの安全にもつながります。些細なことでも迷ったらまず報告してくださいね」と呼びかけました。
そのほか、ある参加者は「ガイドヘルパーを始めたおかげで、町なかで困っている視覚障害者に話しかけられるようになった」という自身の変化を述べ、「先日声をかけた人がたまたまSpotliteに載っていた利用者さんで、お茶して帰りました」と素敵な偶然を語りました。運営チームは「利用者さんのなかには、道で助けてくれた人を『ガイドヘルパーになりませんか?』とスカウトしてくれる人もいるんですよ!」と明かしました。

今回の研修では、ガイド技術をすでに身につけている経験豊富なヘルパーを対象に、より質の高いコミュニケーションスキルの習得を目指しました。野村さんの専門的な指導により、日常的に行っているコミュニケーションを技術的な観点から振り返っている様子がうかがえました。また、参加者同士の雑談では、困難な場面での対処法や、利用者との関係性の築き方について貴重な意見が交換されました。
同行援護は1対1の支援だからこそ、ヘルパー同士の情報交換や経験共有の機会が重要です。みつきでは今後も、こうした研修や交流の機会を通じて、質の高い支援ができるヘルパーの育成と、ヘルパー同士のつながりづくりを継続していきます。
執筆・写真撮影:白石果林
編集協力:株式会社ペリュトン